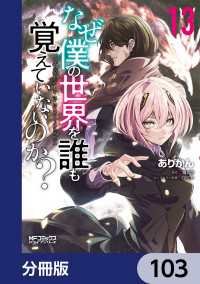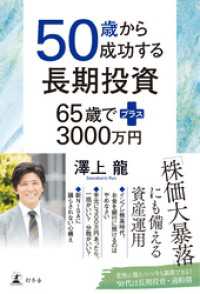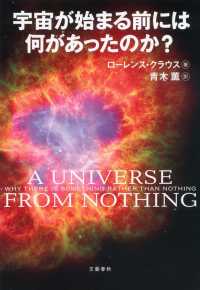- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
怪談や怪奇現象、秘境、未確認生物などをめぐる説話は、ネット時代にどのように伝承されているのか―「都市伝説」「オカルト」「噂話」などの奇妙な「ハナシ」がインターネット上で増殖していく仕組みを「2ちゃんねる」などの掲示板を中心に、SNSや動画共有サイトも視野に入れて明らかにする。
目次
序 説話とコミュニケーション
第1章 ネットロア「くねくね」と電承体について
第2章 再び「くねくね」と電承体について
第3章 『探偵!ナイトスクープ』の「謎のビニールひも」について
第4章 「八尺様」とネットの身体について
第5章 鳥居みゆきの黒い笑いについて
第6章 『あまちゃん』がいる「郷土」について
第7章 「南極のニンゲン」とネット時代の「秘境」について
著者等紹介
伊藤龍平[イトウリョウヘイ]
1972年、北海道生まれ。台湾・南台科技大学教員。専攻は伝承文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
62
「くねくね」や「八尺様」「南極のニンゲン」といった、ネット上での怪談を世間噺の地平で論じた一冊。こういうのは興味本位の対象としてはあったけど、まともに論じられた事は自分の知る限り無いので研究それ自体がありがたい。考証自体は発展から拡散、ネット上の立ち位置を辿ったもので、先行するものが無いためか何となく手さぐりな感じも受ける。考証自体も興味深く読めたけど、読みながら思い出したのはネットが半分アンダーグラウンドであった当時の空気。怪異だけに留まらず、当時のネットと世間の関わり合いも論じた好著でありました。2016/03/04
ゲオルギオ・ハーン
23
ネットロアの紹介本かと息抜きのつもりで読んだが、ネットにおける伝承(本書では『電承』と名付けている)の特徴と誕生の法則性について考察した面白い本だった。所々鋭いと思わせる指摘がある。例えば、情報が不十分だからこそネットロアが誕生し、話が再生産される(くねくねや八尺様)一方、ネットがなければ噂話としてもっと成長していたが実際の番組映像がネット上で存在したため沈静化した事例(探偵!ナイトスクープの謎のビニールひも)を出してとても分かりやすい。2021/09/07
Tanaka9999
18
2016年第1刷、青弓社の単行本。少し古い時点、よく言えば過渡期時点を語っている。ただ現在につながる動画等の言及も薄っすらとあり、さらに新しいものも古い手法での解析も有効との言葉もある。分析の対象となっている現象が古いのは確かだが、現在の状況の分析の基のひとつにはなるであろう。2024/07/06
くさてる
18
「くねくね」や「探偵ナイトスクープ」の謎のビニールひも、八尺様という、ネットによって広がっていった都市伝説やオカルトネタと、ネットを媒介して人口に膾炙していった「鳥居みゆき」や「あまちゃん」現象などについて解説、分析した一冊。あくまで真面目に、しかし分かりやすくまとめられていたのが良かったです。あまりに膨大で、いつでもあるようで不意に消えてしまうネットという媒体で広がっていく話にはまだまだ奥がある気もしますが、面白い一冊でした。2016/07/18
緋莢
16
図書館本。宮部みゆき『宮部みゆきが「本よみうり堂」でおすすめした本』(中公新書ラクレ)で取り上げられており、興味を惹かれた本。説話伝承には口承(口頭による伝承)、書承(文字による伝承)があるが、現代はインターネットの存在が欠かせないものとなっており、それを電承(ネットロア)と呼ぶ、と「序」に書かれています。取り上げられている「くねくね」、「八尺様」等は、普段、積極的に怖い話に 接しようとしなかったので、詳しく知ったのは、つい最近。NHK BSで放送していた(続く 2024/04/12