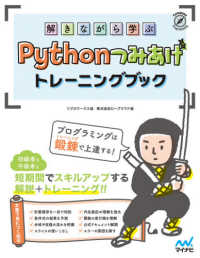出版社内容情報
日本が世界に誇る神経質・神経症の根本的な治療法を、創始者である森田正馬博士がその理論的基盤から応用に至るまで、豊富な症例を用いて解説した必読の名著が新版で登場。精神医療に携わる方、パニック障害や対人恐怖に代表される社会不安、不潔恐怖など心の問題を抱えて悩んでいる方にとって、その方面の治療に世界でも類を見ない成果を挙げた森田療法を学習し身につけるには、けっして欠かすことのできない一冊。
目次
第1編 神経質の本態(私のヒポコンドリー性基調説;私の精神交互作用説;意識と注意に関する私見;神経質の分類;神経質の原因的関係;神経質の病類位置と精神的変質の分類)
第2編 神経質の療法(本療法の原理;一般神経質に対する私の特殊療法;本療法による治療効果;発作性神経症の療法;強迫観念症の療法;説得療法;神経質療法の治験から得る応用方面)
著者等紹介
森田正馬[モリタマサタケ]
1874‐1938。東京大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学教授。神経質症の治療に独自の療法を創始した
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koji
8
日経日曜朝刊「半歩遅れの読書術」で渡辺利夫先生が紹介していました。私はやや閉所恐怖症の気があり、強い関心を持って読みました。学術書と一般向けの中間と言った所で、やや難しい所が多いのですが要約します。森田療法によると、神経症=ヒポコンドリー性基調☓精神交互作用と表され、治癒後も感覚執着が起こると説明します。本書では治療法が詳しく書かれていますが、何より神経質を「あるがまま」に受け入れることが鍵概念で、ここに救済を感じました。今から見ると時代がかった記述も多いのですが、新たな知見を与えてくれたことに感謝します2015/12/22
Asakura Arata
3
今書いている原稿の参考として再読した。色々新しい発見があり。仏教的な例えが腑に落ちることが多くなった気がする。現在の「神経発達症」が当時の診断のどれに近いかを考えた。また、森田神経質が少なくなった理由を、当時の臨床での患者の言動の内容から考えた。2025/07/19
つなぐ
3
神経質という気質には、このような良い面があって、あるがままに生きればこんな良い面があるのだという本を期待してたんだけどちょっと違った。森田療法の学術的な解説が中心で、説得すると症状にさらに注目させてしまうという点を指摘している事が印象的。認知行動療法が症状の成り立ちを質問法を用いながら説得的に引き出していくのと対象的で面白い、認知はあるがまま放っておく事、認知があっても経験からその矛盾に気づかせる事、とっても行動療法的な治療法。認知行動療法で認知をターゲットにしてしまう事の矛盾に気付かされる貴重な一冊2018/11/15
ヤス
3
神経症というのは「気にしまい、考えまい」と何度もその対象となる考えを、強化、学習した結果生じる「思考の癖」なのだろう。しかしこの事を患者が理解したところで、「考えまい」と考えた時点でそのことを「考えている」わけだから、解決は非常に難しい。本当にそのことを考えない状態とは「考えない」という考えすら、消失した状態である。「A」を脳から駆逐するためには、別の「B」ということで先に占有するしかないのかもしれない。眠れない夜に羊を数えるように。なぜなら、脳は二つのことを同時には考えられないからだ。2015/05/23
Asakura Arata
2
文章に「とらわれ」がない。その点清々しく読める。 今も昔も医療の抱える問題って変わっていないのがよくわかる。2009/10/11