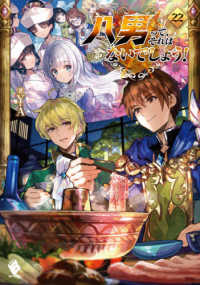内容説明
肉の細胞を培養して食肉(クリーンミート)をつくる―。これは、もはやSFではない。アメリカ、オランダ、日本でも、バイオテクノロジーのスタートアップが、このクレイジーな事業に大真面目に取り組み、先を見据えた投資家たちが資金を投入している。大量の水と土地と時間をつかって穀物を収穫し、食肉にするための動物に与えて育て、殺し、人間が消費する。地球環境にとっても動物にとっても問題があるこのやり方は、いまフードテックによって大きく変わろうとしている。
目次
第1章 培養肉をつくる
第2章 科学の進歩で動物を救う
第3章 グーグル創業者からの支援を武器にする
第4章 培養レザーで先陣を切る
第5章 クリーンミート、アメリカ上陸
第6章 プロジェクト・ジェイク
第7章 食品(と物議)を醸す
第8章 未来を味わう
著者等紹介
シャピロ,ポール[シャピロ,ポール] [Shapiro,Paul]
クリーンミートを食べた最初の人類に数えられると同時に、TEDxの講演者にして、動物愛護の組織「Compassion Over Killing」の設立者。また、最近「動物愛護の殿堂」入りを果たした。日刊紙から学術雑誌に至るまでさまざまな媒体で、動物に関する記事を多数発表している
鈴木素子[スズキモトコ]
埼玉大学教養学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鱒子
94
図書館本 動物由来の食品を人工的に作る試み。そこに肉迫したノンフィクション。牛ひき肉、フォアグラ、チキンナゲット、ヨーグルトなど、現時点でもさまざまなプロジェクトが動いています。惜しむらくは、本書の著者がヴィーガンなので、笑っちゃうほど食レポが下手です(笑。技術としてはまだそこまでは行かないようですが、わたし個人的には牛ステーキを食べてみたいです。いつか日本人が牛レバ刺しを食する日が、また来るかもしれませんね。知らない世界を垣間見る良書でした。2020/04/07
Willie the Wildcat
82
読後、まず頭に浮かぶのが、人間のご都合主義と、先入観・偏見。家畜が動物愛護法の対象外なのが前者の代表とすれば、遺伝子組み替えvs.合成生物学が後者。様々な事例を数値で語る中、皮革製品の件がコラー氏提唱の『”工業的”畜産の4つの不都合』が語る課題。如何に人間の欲が、自然界を歪めているかを象徴している感。自分を振り返っても、乳牛の生産過程は把握していたが、深く考えることなく日々消費している。一方、理想論で語らない著者提言。「時々幸せに育てられた幸福な動物の肉を楽しむ」が、”現時点”での現実解かもしれない。2020/08/15
TATA
45
持続可能な肉食のために選択肢を増やすべきとの論理構成。大豆などの植物性蛋白質によるオルタナティブミートの他に、研究室での培養肉による生産拡大を進めるべきと。厳しい飼育状況、抗生剤の濫用、環境破壊と考えれば説得力のある論説に感じるが、欧米によく見られる動物愛護の考え方が根底にあることにも気付かさせられる。こちらに住んでいるとその考え方に理解する部分もあるが、やはり今の多くの日本人からは乖離の大きな考え方に映る。2020/12/27
sayan
38
機内で本書を手に取り、到着後、早速近くの食料品店に入り培養肉の一つビヨンドミートを購入する。残念ながら日本では培養肉は市販されていない。埼玉県にあるAlisanカフェで代替ミート(大豆)を使ったバーガーが抜群に美味しい。そんなわけで動物を丸ごと飼育せずに畜産物を生産する事業に乗り出した企業のスタートアップを描いた本書は興味深かった。小説オリクスとグレイ(M・アトウッド)に言及し、Ethicalビジネスで強い思想的な下りは最小限で、投資家、顧客の視点に向き合い、市場獲得を目指し事業を構築する下りが刺激的だ。2020/02/12
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
32
僕自身はこの技術に大賛成だ。農学が世界を変える様は修めた者として誇らしい。動物愛護主義的ヴィーガンの主張に反することのない技術なので、この技術が確立されて商業ベースに乗った時に彼らがどんな選択をするのか(果たして彼らはこのクリーンミートを食べるのか否か)についても興味が湧いた。2020/03/21