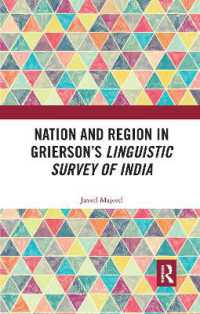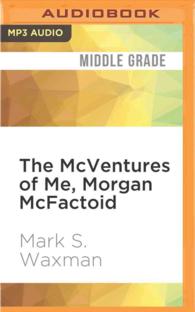内容説明
「本質をとらえたモデル」は、変更に強く、美しい!問題を浮き彫りにし、解決していくモデリングの過程を詳説!効果的な情報システムを設計しよう。
目次
第1部 モデリングの理論(情報システムとモデリング;型図の作成技法)
第2部 モデルの展開(概念レベルから実装レベルへ;パタンとリファクタリング;ビジネスモデリングへの適用)
第3部 モデリングの実践(演習1:酒問屋の在庫管理;演習2:航空券の予約;演習3:酒問屋をもう一度)
著者等紹介
児玉公信[コダマキミノブ]
北海道札幌市出身。東京都立大学人文学部(心理学専攻)卒。石油元売り、北海道大学受託研究員、鉄鋼系情報子会社を経て、現在、情報システム総研取締役副社長/モデラー。システム思考に基づく問題認識からモデリング、情報システムのアーキテクティングとコンサルテーションに従事する。技術士(情報工学部門)、博士(情報学)。産業技術大学院大学、青山学院大学、静岡大学各非常勤講師。情報処理学会技術士委員会委員長、同情報システムと社会環境研究会幹事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
21
制約に関する姿勢がよい。 UMLが膨大になっているので限定的に用いているとのこと。 事例として酒問屋の在庫管理がある。 図6.2 リッチピクチャー がわかりやすい。 CATWOE customer, actor, transformation, weltanschauung, owner, environment 揺さぶり。「後で起こりうる要求変更を想定してモデルを検証し、改良する」 OCLで制約を記述する。 シーケンス図で責務を割り当てる。 航空券の予約の事例もある。 2020/03/08
monotony
3
ある程度自分でモデル書いて試行錯誤した経験のある人(中級者)向けの本でした。UMLが読める程度では肝心の本質を理解することは難しく見事に撃沈。出直してきます。うんうん頷きながら読めるぐらいのスキルは身に着けたい。2016/09/14
とりもり
2
「入門」と異なり、内容はかなり難解。途中からは読んで何とかついていくのがやっとという状態。モデリングの重要性はよく理解できたが、これを自分で書けるかというとちょっと…。但し、モデルに「揺さぶり」をかけることで本質が見えてくるというプロセスには感銘を受けた。こうした本質を見出すやり方自体は、モデリング以外にも応用可能だろう。その意味で、UMLモデリングはプログラミングだけのものではなく、ビジネスプロセスにも十分応用可能なスキルだと感じた。いつか再読したい一冊。★★★☆☆2017/11/07
yuji
2
概念レベルの型図において要求者が言わなかった業務、未来の予測を加えて、「揺さぶる」「引いて眺める」はとても重要、とりあえず線を繋ぐ人が多いのでインスタンス図で現物確認も重要。一番知りたい型図⇒クラス図⇒コードを具体事例で追体験することが、そこまで丁寧には書かれていなかったのが残念である。P.99クラス図のファサードクラスがP.103に書かれていないのが納得いかない。参考文献が多数のっているので他に当たってみるか。OCLというのも正確に表現するには有効だがなかなか手強い。いまいち理解できなかった。2014/02/14
もりひろ
2
児玉さん、変わってないなあ。UMLの様式だけを見よう見真似で分かった気になっているだけでは仕事には使えないことが改めて理解できた。なるほど、これならUMLを使いたくなる。2012/07/14
-
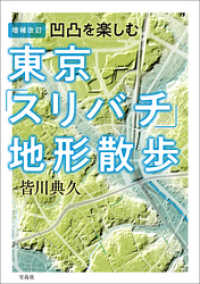
- 電子書籍
- 増補改訂 凹凸を楽しむ 東京「スリバチ…