- ホーム
- > 和書
- > コンピュータ
- > プログラミング
- > SE自己啓発・読み物
出版社内容情報
ITの現場では、要件定義書や設計書をはじめとする、たくさんの文書が行き来する。文書の中には、絵や図なども書くが、情報を伝える上で一番大事なのはなんといっても文章である。いくら絵や図をきれいに書いたとしても、それだけでは仕事に必要な情報をくまなく伝えることなどできないからだ。
文章の中に、たとえ一部であっても、分かりにくくて誤解を招く表現があると、ITの現場は大混乱に陥ってしまう。文章がシステム開発プロジェクトで使われるものの場合、誤解を招く表現があるとバグや性能不足など重大な欠陥に発展することがあるからだ。それをなんとか食い止められたとしても、問題を解消するために多くの関係者に余計な手間や時間を取らせることになり、結果的に全体の生産性や品質の悪化につながってしまう。
本書は、ITエンジニアが仕事で作成する文書を分かりやすくて、読みやすく、しかも誤解のないものにするためのコツやヒントを示すことを狙ったものである。
【解説編】
第1章■正しい日本語
速く読めて誤解がない書き方にはコツがある
・速く読める文章を書くコツ
・理解が一致する文章を書くコツ
第2章■時系列の表現
同時並行か順番か、補足説明で誤解を防ぐ
(?T)「~する」の時制を明確に
(?U)「~まで」には補足を付ける
(?V)体言止めは使わない
・コラム「メッセージが伝わる文章を書くコツ」
第3章■箇条書き
説明文を付けてシンプルに表現する
(?T)箇条書きの前に説明文を付ける
(?U)上位概念を一つにそろえる
(?V)「割り込み箇条書き」にしない
(?W)項目を短く表現する
第4章■抽象表現と例示
ついつい使う抽象語が認識のズレを生む
(?T)いろんな意味を持つ二字熟語
(?U)何を示すのか分からないカタカナ語
(?V)書き手だけに明瞭な言葉
第5章■要約・見出し
要点がすぐ分かるように徹底して枝葉を削ぐ
・要約(?T)徹底的に枝葉を削ぐ
・要約(?U)概要に書く項目を決める
・見出し(?T)話題は一つに絞る
・見出し(?U)結合する概念は二つまで
・見出し(?V)曖昧な言葉は使わない
・見出し(?W)区別不能な複合語は見直す
・見出し(?X)「その前に」は後回し
第6章■骨子作りと推敲
書いた文章を見直して納得感を高めよう
(?T)目的を盛り込む
(?U)三角ロジックを活用する
(?V)階層構造で目的と手段を整理
(?W)一晩寝かせてチェックする
【演習編】
第7章■曖昧表現(多義文)をなくす
複数解釈が可能な説明文、紛らわしい係り受けを正す
・複数の解釈ができる条件説明の修正
・格助詞の「の」に要注意
・どっちもありの「係り受け」
・「~れる」「~られる」は避ける
・「が」は順接なの?、逆接なの?
・強調語に注意
第8章■文字数を減らして読みやすくする
一つの文章には一つの事柄、漢字の割合を30% 程度にする
・一文一義主義
・単文と重文、複文
・and/or/xor はどう表現すればいいのか
・ひらがなの羅列を減らす
・漢字を多用すればよいわけではない
第9章■否定文を使わない
文字外の広がりは負の要因、肯定文に変えよう
・否定文は誤解を招く
・部分否定文を肯定文に変える
・二重否定文を肯定文に変える
・準否定は具体化する
・否定文でなければ表現できないケース
・コラム「AはBのように○○ではない」
第10章■時系列の表現に要注意
時間感覚のずれ発生を防ぐ、時制をはっきりさせよう
・「~する」の時制はなに?
・「~するとき」とは、する前か後か?
・「~まで」の表現では補足説明をする
・「~以上」「~以下」「~を超える」「~未満」
・体言止めや用言の語尾省略は避ける
第11章■分かるようで分からない抽象表現
曖昧で正しく伝わらない、相手に応じて抽象度を設定
・抽象的とはどういうことか
・外来語に由来する抽象的な用語
・分かった気になっても本当はよく分からない
・カタカナ語は便利だけど意味が不鮮明
・別のものに置き換えて表現する比喩表現
・「抽象的=悪い」ということではない
・コラム「日本発の二字熟語を中国が逆輸入」
第12章■信頼されるSEになるために―日本語の常識
回りくどい表現を避ける、総合演習問題で仕上げ
・「もの」「こと」が多いとまどろっこしい
・「を行う」は軟らかいけど回りくどい
・主語と述語の対応が取れないと理解不能に
・総合演習問題で総仕上げ
内容説明
前半の解説で知識を棚卸し、後半の演習で徹底的に訓練。設計文書の作成に必須のスキルをスイスイ習得。
目次
解説編(正しい日本語―速く読めて誤解がない書き方にはコツがある;時系列の表現―同時並行か順番か、補足説明で誤解を防ぐ;箇条書き―説明文を付けてシンプルに表現する;抽象表現と例示―ついつい使う抽象語が認識のズレを生む;要約・見出し―要点がすぐ分かるように徹底して枝葉を削ぐ;骨子作りと推敲―書いた文章を見直して納得感を高めよう)
演習編(曖昧表現(多義文)をなくす―複数解釈が可能な説明文、紛らわしい係り受けを正す
文字数を減らして読みやすくする―一つの文章には一つの事柄、漢字の割合を30%程度にする
否定文を使わない―文字外の広がりは負の要因、肯定文に変えよう
時系列の表現に要注意―時間感覚のずれ発生を防ぐ、時制をはっきりさせよう
分かるようで分からない抽象表現―曖昧で正しく伝わらない、相手に応じて抽象度を設定
信頼されるSEになるために-日本語の常識―回りくどい表現を避ける、総合演習問題で仕上げ)
著者等紹介
上田志雄[ウエダユキオ]
ティージー情報ネットワーク基盤戦略推進部技術・データ基盤グループマネージャー。国際衛星通信アンテナ建設からシステム開発まで幅広い分野のプロジェクトを経験。日本情報システム・ユーザー協会主催「ソフトウェア文章化作法若手向け」講師
島田悟志[シマダサトシ]
ティージー情報ネットワーク基盤戦略推進部長補佐兼技術・データ基盤グループマネージャー。海外向け電話交換機のITエンジニアとして提案書の作成を経験。さらに日本航空でシステム設計指針の策定、ドキュメントの標準化などに従事した後、2010年にティージー情報ネットワークに入社し、2011年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 女装じいさんと男装ばあさん【分冊版】 …
-
![[音声DL付き]CNN ENGLISH EXPRESS 2020年11月号](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0909421.jpg)
- 電子書籍
- [音声DL付き]CNN ENGLISH…
-
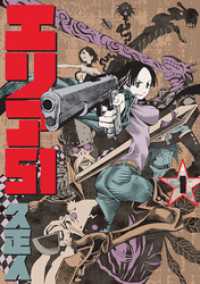
- 電子書籍
- エリア51 1巻 バンチコミックス
-

- 電子書籍
- 実践コンピューターリテラシー入門
-
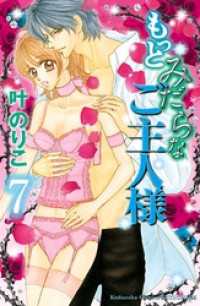
- 電子書籍
- もっとみだらなご主人様 分冊版(7)




