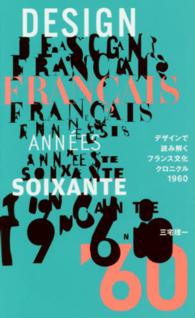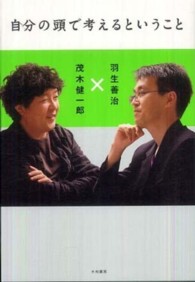- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > ビジネス教養
- > IoT・AIビジネス
出版社内容情報
AIの開発・活用において日本はもはや“後進国”
巻き返しのカギは若きAIチャレンジャー
AIの開発・活用において日本はもはや“後進国”
巻き返しのカギは若きAIチャレンジャー
「日本のディープラーニング・ビジネスは、米国はもとより
中国の台頭ぶりを見れば、世界で勝てる感じがしない、敗戦に近い。
ただし、人材の育成に取り組み、若い優秀な人材に権限委譲すれば、
様々な産業領域で世界一になれる可能性はある」
東京大学大学院特任准教授 松尾豊氏
米国企業はもとよりアリババ集団やテンセントなどの中国企業に比べても、
日本企業がAI活用のビジネスで大きく出遅れているのは紛れもない事実だ。
海外で開催されているAI関連の国際学会への論文採択数などでも、
米国や中国に比べて日本は極端に少ない。
まさにAI後進国ニッポンだが、
それでもAIを駆使して世界を切り拓く挑戦者たちがいる。
例えば、東京大学発スタートアップ企業のエルピクセル。
同社は、複数の医療機関と連携してライフサイエンス分野でAIによる
画像解析のソリューションを開発している。島原佑基代表取締役は
世界最大の放射線医学フォーラムで講演し、世界進出の第一歩を踏み出した。
NEC史上最年少の主席研究員となった藤巻遼平氏は、データ分析プロセスを
自動化するAIスタートアップ企業、ドットデータを米国に創業して
自らCEO(最高経営責任者)に就任する予定だ。
「脱出のカギはディープラーニング人材の育成」にあると見込む
松尾特任准教授は、日本ディープラーニング協会を設立し理事長に就任。
教育検定資格を通じて人材育成に乗り出した。
本書では、いま、日本で起こっているAI、中でもディープラーニングを活用した
ビジネスの動向をダイナミックに描き、コマツ大橋徹二社長(兼)CEO、
リクルートホールディングス峰岸真澄代表社長兼CEO、経営共創基盤(IGPI)
冨山和彦代表CEOら、優れた経営者へのインタビューから
日本企業が進むべき道を示す。
第1章 AI後進国ニッポン
INTERVIEW NEC 藤巻 遼平 氏
第2章 それでも世界に挑むAI人材
INTERVIEW Preferred Networks 奥田 遼介 氏
第3章 ディープラーニング人材を育成して日本を救え!
第4章 AI後進国脱却へ、変革を急ぐ企業
INTERVIEW 本田技研工業 松本 宜之 氏
INTERVIEW コマツ 大橋 徹二 氏
INTERVIEW リクルートホールディングス 峰岸 真澄 氏
第5章 ディープラーニング・ビジネスの可能性を知る
INTERVIEW 経営共創基盤 冨山 和彦 氏
多田 和市[タダ ワイチ]
著・文・その他
目次
第1章 AI後進国ニッポン(AIの開発や活用で日本は明らかに出遅れている;得意分野でも、あっという間に追い抜かれた日本企業 ほか)
第2章 それでも世界に挑むAI人材(グローバルへの第一歩を踏み出す;日本で3次元診断の腕を磨く ほか)
第3章 ディープラーニング人材を育成して日本を救え!(優秀な若者はAIを学んでいる;学生自らが場づくりに乗り出す ほか)
第4章 AI後進国脱却へ、変革を急ぐ企業(ホンダの強みの源泉はアシモ;オムロン、AI活用で一日の長 ほか)
第5章 ディープラーニング・ビジネスの可能性を知る(自動車販売の現場で売りやすく;保険提案の打数を増やす ほか)
著者等紹介
多田和市[タダワイチ]
1985年3月、慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。同年4月、日本経済新聞社入社。「日経エレクトロニクス」記者、「日経ビジネス」記者を経て、99年、「日経ビジネス」副編集長。2003年3月から「日経情報ストラテジー」副編集長。2004年1月から同誌編集長。2010年1月から「日経ビジネス」編集委員。2010年12月から日経BPビジョナリー経営研究所長。2013年4月から同上席研究員。2014年1月から「日経ビッグデータ」記者。2018年4月から新媒体「日経クロストレンド」シニアエディター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
vinlandmbit
こもも
syatsuzuka
sumiyaki
suoyimi