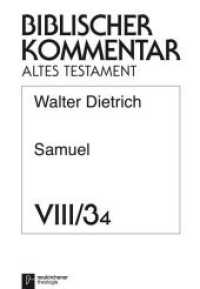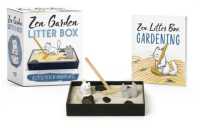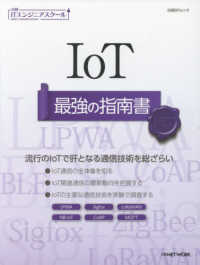出版社内容情報
子どもたちを真のデジタルネイティブである「クリエイティブ・シンカー」(創造的思考力・発想力を身に付けた人)に育てるにはどうしたらよいのか――。
そのために、大人たちはどのように振る舞えばよいのか――。
プログラミング言語「Scratch(スクラッチ)」の開発者が世に問う、人生100年時代の新しい教育論。
世界が、子供だけでなくすべての人にとっての創造的な思考と学びの大切さについて理解し始めるにつれ、メディアラボにおけるミッチの役割とライフロング・キンダーガーテン・グループの取り組みは、ますます重要になっています。
(中略)
ミッチが掲げる4つのPの原則(Projects, Passion, Peers, Play)は、メディアラボの大学院生の教育プログラムはもとより、世界中で数百万の子供たちが利用しているプログラミング環境(言語でありコミュニティでもある)スクラッチ(Scratch)の基盤となる考え方です。
(中略)
私の願いは、この本が「急速に変貌する世界で生き残るためのコンパス」としての役割
を果たすことです。
――日本語版序文より
この本は、子供、学び、創造性を気にかける人たち、子供たちのために玩具やアクティビティを選ぼうとしている保護者たち、生徒が学ぶ新しい方法を探している教育者たち、新しい教育体制を取り込もうとしている学校管理者たち、子供のための新しい製品やアクティビティを生み出そうとしている開発者たち、あるいは単純に子供、学び、そして創造性に興味を持つ人たちに向けて書かれています。
――第1章 創造的な学びより
日本語版序文 伊藤 穰一
序文 ケン・ロビンソン
第1章 創造的な学び
A学生からX学生へ
ライフロング・キンダーガーテン(生涯幼稚園)
クリエイティブ・ラーニング・スパイラル
4つの基本原則にチャンスを
創造性についての誤解
技術に対する葛藤と矛盾
自分の声で:他リーン
第2章 プロジェクト(Projects)
メイカーたち
メイキングを通した学習
考えるための玩具
スクリーン上の創造性
流暢に表現できる能力
知識に対する葛藤と矛盾
自分の声で: ジョレン
第3章 情熱(Passion)
興味を持って作り上げる
広い壁
ハードファン
ゲーミフィケーション(ゲーム化)
パーソナライゼーション(学びの個別化)
構造に対する葛藤と矛盾
自分の声で:ジャリサ
第4章 仲間(Peers)
ロダンを超えて
学習コミュニティ
開放性
ケアの文化
教えること
専門知識に対する葛藤と矛盾
自分の声で:ナタリー
第5章 遊び(Play)
遊び心
ベビーサークルと遊び場
ティンカリング
多くの道筋と多くのスタイル
トライ、何度でもトライ
自分の声で: ジミー
第6章 創造的な社会
100の言葉
学習者のための10のヒント
親と教師のための10のヒント
デザイナーと開発者のための10のヒント
ライフロング・キンダーガーテンへの道
補章 創造的な学びの体験
創造的な学びについてさらに理解を深めるためのオンライン講座
「ラーニング・クリエイティブ・ラーニング」 村井 裕実子
参加者の主体性に基づく、
変化を前提としたScratchワークショップの実践 阿部 和広
さらなる文献とリソース
謝辞
ミッチェル・レズニック[ミッチェルレズニック]
著・文・その他
村井 裕実子[ムライユミコ]
著・文・その他
阿部 和広[アベカズヒロ]
著・文・その他
伊藤 穰一[イトウジョウイチ]
著・文・その他
ケン・ロビンソン[ケンロビンソン]
著・文・その他
酒匂 寛[サコウヒロシ]
翻訳
内容説明
小学校のプログラミング教育に賛成の人も反対の人も、この本を読まずして語れない。開発者自身がいま明らかにするスクラッチの真の目的。
目次
第1章 創造的な学び
第2章 プロジェクト(Projects)
第3章 情熱(Passion)
第4章 仲間(Peers)
第5章 遊び(Play)
第6章 創造的な社会
補章 創造的な学びの体験
著者等紹介
レズニック,ミッチェル[レズニック,ミッチェル] [Resnick,Mitchel]
教育テクノロジーの専門家であり、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボのラーニング・リサーチ(学習研究)の教授である。30年にわたり玩具会社のレゴ社と緊密な協力を続け、レゴ マインドストーム・ロボットキットなどの革新的なプロジェクトを共同で成し遂げてきた。MITでレゴの寄付講座も開講している。またプログラミング環境であると同時にオンラインコミュニティでもあるスクラッチ(Scratch)を開発するチームのリーダーを務める。低所得者コミュニティの若者たちのための課外学習センターのネットワークである、コンピュータクラブハウス・プロジェクトの共同創立者でもある
村井裕実子[ムライユミコ]
慶應大学メディアデザイン研究科修士課程、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ博士課程を経て2016年よりマサチューセッツ工科大学メディアラボ博士研究員。デジタルテクノロジーを使った学習環境づくり、特にピア・ラーニングにおける自信ややる気の仕組みについて研究している。ものづくりを通して学ぶクリエイティブ・ラーニングを実践する教育者やデザイナー、保護者のためのオンラインまたはハイブリッド学習コミュニティづくりに取り組んでいる
阿部和広[アベカズヒロ]
1987年より一貫してオブジェクト指向言語Smalltalkの研究開発に従事。パソコンの父として知られSmalltalkの開発者であるアラン・ケイ博士の指導を2001年から受ける。Squeak EtoysとScratchの日本語版を担当。近年は子供や教員向けの講習会を多数開催。OLPC($100 laptop)計画にも参加。2003年度IPA認定スーパークリエータ。青山学院大学客員教授、津田塾大学非常勤講師。文部科学省プログラミング学習に関する調査研究委員
酒匂寛[サコウヒロシ]
1980年代初頭に獣医学部を卒業後、ソフトウェアの世界に転進。メインフレーム、ミニコン、ワークステーション等のソフトウェア開発者を経てソフトウェア開発コンサルタントとして活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
エリナ松岡
まっちー
Motoaki Nakashima
よしたけ
mkisono