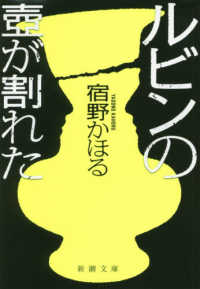内容説明
取引コスト経済学が読み説いた人類一万年の「制度」の進化論。ノーベル経済学賞受賞者による目から鱗の世界史。
目次
第1部 理論(問題提起;経済の構造―序論;新古典派流の国家理論;歴史上の経済機構―分析の枠組み;イデオロギーとフリーライダー問題;経済史の構造と変化)
第2部 歴史(第一次経済革命;第一次経済革命―機構への影響;古代文明の経済変化と衰退;封建制の発達と崩壊;近世ヨーロッパの構造と変化;産業革命再考;第二次経済革命とその帰結;アメリカ経済の構造と変化)
第3部 理論と歴史(制度変化の理論と西洋経済史)
著者等紹介
ノース,ダグラス・C.[ノース,ダグラスC.][North,Douglass C.]
1920年生まれ。ロナルド・コース、オリバー・ウィリアムソンらと並ぶ新制度派の経済学者。歴史研究に新制度派の理論を応用した研究で業績を残した。経済史に経済理論や数量分析を導入した功績で1993年にノーベル経済学賞を受賞
大野一[オオノハジメ]
翻訳家。外資系企業に勤務するかたわら、翻訳に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まるさ
5
私有財産や市場などの制度と経済成長の関係性について歴史を紐解きながら論じている。フリーライダーについて相当神経を払っている。2017/01/21
NUTUTMUHSTII
2
経済、政治、そして広くは社会のあり方が何によって規定されるか、そしてどのように変化するか、というテーマを論じている。 狭い意味での経済学に加えて、土地と労働力の相対価格、軍事技術(の偏在)、技術ストック、イデオロギー・道徳、所有権にまつわる制度、組織・機構、収穫逓減、疎外、機会主義、といった要素を取り込んだ均衡力学によって、主として欧米諸国の歴史上の経済・政治制度の変遷を理解しようと試みる。 第2部の歴史編は面白く、かつ頭がいっぱいになった。第1部と第3部は抽象的一般論過ぎてわたしにはツラい。2018/02/27
belier
2
さすがにノーベル経済学賞を受賞した経済学者らしく明晰に経済史を説明している。しかし「イデオロギー」によってルール破りを防止されてきたのが重要だったと強調する割りに、イデオロギーがなぜ生じるかの深い分析が示されてない気がした。また、第二次経済革命のおかげでヨーロッパが繁栄したとするが、植民地政策による搾取があったからこその繁栄ではないのかという疑問も生じた。解説にあるような「なぜ非効率な制度が存続するのか」への深い洞察は、学のない自分には残念ながら読み取れなかった。2017/11/07
ぽてと
1
所有権やイデオロギーに着目して西洋経済史を読み解こうとした本。フリーライダー問題が重要と述べつつも説明があまり掘り下げられていないのは不満だが、個人的には経済史はアナール学派を少しかじったくらいだったので、所有権や経済革命を重視する視点が新鮮だった。2015/12/17
megane
0
割とはやりの歴史と経済をまぜたような奴だ。農業が発展して支配層が出てきてみたいなやつ。古い本なので、後発の似たような本を色々読んでいたため内容かぶってたから個人的にはあんまりおもしろくはなかったかな。本自体は良いと思う。もっと早く出版されてたらよかったのに。2013/09/18



![マーク式基礎問題集英語[語句整序] 河合塾series (八訂版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47772/4777228940.jpg)