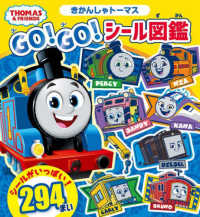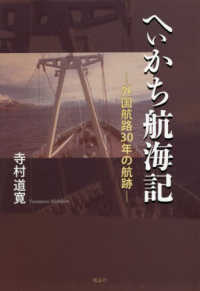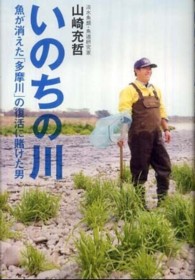目次
第1章 多様化する義務教育
第2章 日本の子どもたちの問題点
第3章 問われる本質的な力
第4章 どれくらい解けるのか。子どもたちの発揮する力
第5章 解ける子・解けない子の違いは
第6章 どうやって伸ばす。学校で・家庭で
著者等紹介
角屋重樹[カドヤシゲキ]
広島大学大学院教育学研究科教授。1949年三重県生まれ。広島大学大学院教育学研究科教科教育学(理科教育)専攻博士課程単位取得退学。博士(教育学)。広島大学教育学部助手、宮崎大学教育学部助教授、文部省初等中等教育局教科調査官を経て、現職。理科教育の改革に邁進(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
凛
5
学んだ知識を使っての応用問題。これを自由に解いていいよと言われたら楽しいだろうな。教育する側が自由度を許容する必要があると感じた。私が小学生の時は先生の求める答えのみが全てで、窮屈な思いをしていた。今思えばそれが全てだったあの頃の世界の狭さが嘆かれる。自分の子供にはもっと多角的な視野を持って欲しいと願う。健康的な生活習慣、家族の対話、家庭学習、家事への協力、これらは親が意識して良い方向に促していきたいと思った。2018/04/01
Tohru Soma
1
10年前の本だけど、今注目されていることがしっかりと書かれている。専門的な人の分析は当たることもあるんだな。(ヤバい経済学には、専門家の予測はチンパンジーがと同じ確率って書いてあったけど) 後半の内容に書かれていることは、自分が書いたらもっと具体的に書けるのに!って思った!2016/03/16
やすたき
0
昨今は教育情報が溢れかえっていて、何が正しいのかわからんけど、この本は起承転結がしっかりしていて読みやすいし統計を元に分析していて説得力がある。独りよがりな新書よりも一冊の本でしっかりストーリーを完成している。さすが教育専門機関。ただ子を塾へ通わすのではなく、保護者が塾機構から何が問題で何をすべきか道しるべを示す必要がある。2017/03/21
にこにこ
0
公立中高一貫校の適性検査問題は頭の体操みたいで面白い。普段の生活で「使える」経験を測る問題みたい。わざわざ受験勉強しなくても受かる子はうかる、ってうのもナットク!2009/11/16