出版社内容情報
あの""お客様""は、なぜキレるのか? 犯罪心理学者が読み解く、現代日本の病。
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、従業員への悪質なクレームや物理的・精神的な嫌がらせ全般を指す。「店員にキレる客」を誰しも見たことがあるように、カスハラは日本で大量発生している。さらに、コロナ禍によって拍車がかかり、被害は拡大している。2022年2月には、厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が発表され、現代日本において大きな社会問題と化しているのだ。本書では、犯罪心理学者として長年カスハラにかかわってきた桐生正幸が、豊富な調査実績を基にカスハラが生まれる構造を分析し、その対策を提示する。
【目次】
・序章 日本のカスハラ事情
・第1章 キレる""お客様""たち
・第2章 カスハラの心理構造
・第3章 ""お客様""の正体
・第4章 カスハラ対策の最前線
・第5章 カスハラ防止法案という希望
・終章 カスハラのない国へ
【著者略歴】
桐生正幸(きりう・まさゆき)
山形県生まれ。東洋大学社会学部社会心理学科教授。日本犯罪心理学会常任理事。日本心理学会代議員。文教大学人間科学部人間科学科心理学専修。博士(学術)。山形県警察の科学捜査研究所(科捜研)で主任研究官として犯罪者プロファイリングに携わる。その後、関西国際大学教授、同大防犯・防災研究所長を経て、現職。著書に『悪いヤツらは何を考えているのか ゼロからわかる犯罪心理学入門』(SBビジュアル新書)などがある。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やっさん
91
★★☆ クレーマーの言動を犯罪心理の観点で読み解いた一冊。「自尊感情が高い人ほど加害行動をとる割合が高まる」というデータはかなり意外だった。きっと無意識のレベルで序列を確定させてるんだろうな。。。2023/08/18
さっちゃん
41
犯罪心理学の観点からクレーマーの心理を分析した一冊。SNSで店員を恫喝したり土下座を強要する「お客様」は単なる犯罪者だ。店舗や商品、接客をより良くするための意見ならいざ知らず、ストレス解消のはけ口にしているとしか思えない。普段スーパーなどでも高圧的な態度の客を目にするが、それを目にするこちらまで気分が悪くなる。このようにきちんと分析して対処方法を考えていくことで、カスハラを生み出さない社会を作っていけたらと思う。「お客様は神様ではなく、おたがい様である」という言葉を大人はもちろん子どもにも学んでほしい。2024/01/31
香菜子(かなこ・Kanako)
17
カスハラの犯罪心理学。桐生 正幸先生の著書。カスハラカスタマーハラスメントを放置すると従業員の心が壊れてしまう。カスハラカスタマーハラスメントには対応しない。カスハラカスタマーハラスメントには毅然とした態度で接する。度を過ぎたカスハラカスタマーハラスメントは犯罪。カスハラカスタマーハラスメントを平気でするような人たちはもしかしたらカスハラカスタマーハラスメントがエスカレートして犯罪をするかもしれない。カスハラカスタマーハラスメントを甘くみると被害が拡大する。2023/08/18
Katsuto Yoshinaga
9
以前はクレーマーと呼んでいたのが2010年頃から“カスハラ”と呼ぶのが一般的になったそうである。その背景には「客のことを悪く言いたがらない企業風土」があり、「クレーマー扱いすると客をよそにとられてしまうから、非がなくても謝る」となったらしい。また、価格以外の手っ取り早い差別化の方法が「おもてなし」と考え、クレームを甘受し対策を怠った結果だと著者は語る。クレーム対応のリスクの方が大きいと考え返品/返金をおおらかに受け付ける欧米とは、マーケティングの意識が根本から違うようだ。(コメに続く)2023/08/19
志村真幸
5
著者は山形県警の科学捜査研究所で犯罪者プロファイリングに携わったのち、大学教授に転身した人物。 本書は、近年問題になっているカスハラ(カスタマーハラスメント)について詳述したもの。単純に表面的な対処法を示すのではなく、カスハラがなぜ起こるのか、どんなひとがカスハラをしがちなのか、というところまで踏みこんで分析している。 数量的/心理学的なデータ化によって、カスハラに関する明確な傾向が出てくるのがすごい。そしてそれによって、ことを荒立てずにカスハラを収める方法が見えてくる。2023/06/14
-
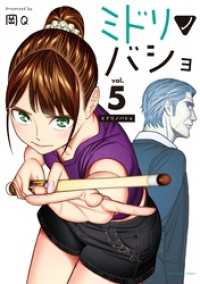
- 電子書籍
- ミドリノバショ(5) マンガワンコミッ…
-

- 洋書電子書籍
-
菊地秀行著『D-薔薇姫』(英訳)







