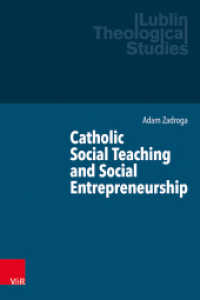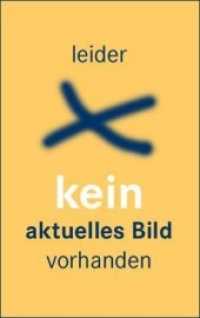内容説明
囲碁史に刻まれる昭和の名著。棋書ベストセラーに輝く影山流名解説、再び躍動。
目次
第1章 シチョウとゲタ
第2章 切りとツギ
第3章 石の歩み
第4章 石の先行争い
第5章 勢力圏と地
第6章 石の死活
第7章 定石の勉強法
第8章 愚形、好形
第9章 本手とうそ手
第10章 手筋
第11章 侵分の心得
著者等紹介
影山利郎[カゲヤマトシロウ]
大正15年生まれ。静岡県出身。昭和23年全日本素人本因坊戦優勝。24年秋プロ転向、初段。28年大手合第2部優勝。36年六段昇段。40、41年第9、10期首相杯争奪戦準優勝。42年高松宮賞受賞。52年七段昇段。棋風は計算に明るく堅実。アマ碁界の発展に尽力し、その指導法には定評があった。ライターとしても活躍、著書多数。平成2年死亡、享年64歳(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kokada_jnet
59
1970年に刊行された、影山利郎七段の名著を、2013年に日本棋院アーカイブとして再刊したもの。アマチュアに参考になる手筋を体系的に整備して説き、現在の目で見ても新鮮。そして「アマとプロの一番大きな違い」の白眉が、第九章「本手とうそ手」。アマの初級者とプロは固い本手を打つが、アマの有段者が「無理に頑張ったウソ手」を打つという内容で、これは目鱗だった。巻末には23歳の青年名人の林海峰に、40歳の影山七段が快勝した棋譜が収録。2023/02/22
gtn
6
小学生の頃、父の書棚から取り出し、初めて読んだ囲碁入門書。内容は何も理解できなかったが、文章に惹かれた。著者が当時の名人林海峯に勝利した自戦記が誇らしげで微笑ましい。2018/06/28
santana01
5
40年以上前に発刊された棋書の復刻版。当時のベストセラーらしいが、梶原九段、中山五段、影山七段や名物ライター諸氏無き今「~節」という語り口が妙に懐かしい。内容は碁の基本的な考え方と勉強法を提示したもので、具体的な問題集のように多くの図を用いてのトレーニング的要素は少ない。碁のルールや本質が変わらない限り古びることはないが、その後により充実した内容の棋書も出版されているので、本書で自分の苦手な分野を把握したうえで、具体的専門書に当たるといった使い方が正しいように思う。2013/11/02
kouki_0524
4
囲碁本を連読。内容的には有段者向けとも思うけど、初心者が犯しがちな過ちに対してその都度自分が当てはまっていたのには笑った。 これも初読ではなんの意味もない本。ちょっと寝かして繰り返し読みたい。2015/12/22
治雄
1
影山六段の名調子が楽しい本でした。僕は、囲碁は素人同然の実力なので、この本でどのくらい棋力が上がるかといったことは、わからないです。でも、面白く読むことができました。2013/12/10
-
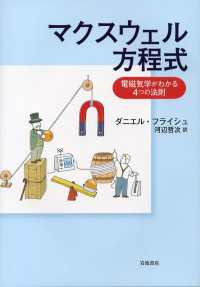
- 電子書籍
- マクスウェル方程式 - 電磁気学がわか…