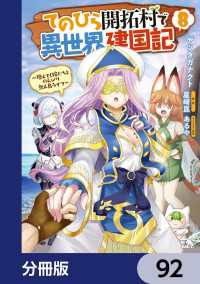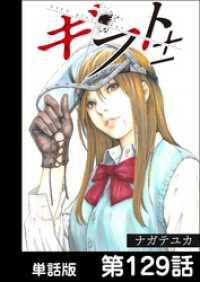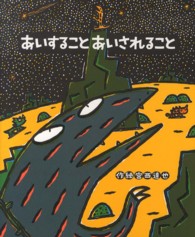内容説明
現代日本の歴史において重要な役割を果たしてきた日教組。膨大な非公開史料や関係者へのインタビューに基づき、リアルな日教組像を明らかにする学術的研究。下巻では、1980年代の労働戦線の再編から、教育運動の転換、文部省との「歴史的和解」まで、新たな路線選択の時代に迫る。
目次
第2部 混迷と和解(社会の変化と日教組;一九八〇年代の労働戦線再編の中で;「四〇〇日抗争」の過程;一九八九年の分裂;文部省との「歴史的和解」の政治過程;一九九〇年代の路線転換と二一世紀ビジョン委員会;一九九五年の運動方針転換への合意形成過程;結論に代えて)
著者等紹介
広田照幸[ヒロタテルユキ]
1959年生まれ。1988年東京大学大学院教育学研究科修了。南山大学文学部助教授、東京大学大学院教育学研究科教授などを経て、日本大学文理学部教授、日本教育学会会長。著書『陸軍将校の教育社会史』(世織書房、1977年、サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件