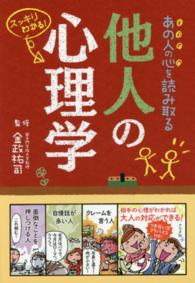内容説明
世界有数の巨大産業の誕生から今日までを、初めて通史として捉えた産業史の決定版。急速な成長と生産過剰のメカニズムを鋭く分析、世界的高シェア企業の叢生など、変容する日本の石油化学産業の新たな潮流も描き出す。
目次
化学産業の概観―大きな産業規模と巨大企業の欠如
第1部 高度成長と設備過剰問題(石油化学産業の勃興期;石油化学産業の高度成長期;大型設備の完工と設備過剰の発生;投資調整の継続と設備過剰の深化;設備投資調整の逆機能)
第2部 化学産業における国際競争力の高まり(日本の化学企業の収益分析;エチレンセンター企業の変革;機能性化学事業の成長による国際競争力の獲得;政府・企業間関係と産業発展のダイナミクス)
石油化学産業の現状と課題
著者等紹介
平野創[ヒラノソウ]
1978年生。2008年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。現在、成城大学経済学部准教授(博士、商学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
24
『産業政策と企業行動』について石油化学産業(PPやPEなどのプラスチック製品などの原料を生産)を対象に研究しが著者の論文をまとめた一冊。経済学や経営学では産業政策の評価は高くない、というのも日本においては戦前から業界団体が調整して見通しや案を考え、それに国が追随したものが主な産業政策の実態であり、国が独自に計画し、業界団体を率いて産業育成を牽引したということはなかったとされている。本書は果たして全てがそうかという疑問からスタートして研究している(果たして学会の通説のとおりかという、研究者らしい出発点)。2022/08/25
のっち
0
日本の石化産業(特に基礎化学品)の成り立ちと数年前(出版年)の特徴を記述している。筆者の目的である、実際の歴史と経営学的な理論を組み合わせ問題提起する視点では少し面白みを感じる。 一方で特に技術的な観点を踏まえた考察が甘いと感じた。化学産業は技術的な観点によるスイッチングコストが高い業界であるため、各メーカーの業績の推移を考察するにあたって触れる必要があると感じた。 また、業績の比較しているが、その背景の考察も薄い。例えば、三井化学の基礎化学品比率が高いことを指摘しているが、背景には触れていない。2022/06/10
-

- 和書
- 僕の家