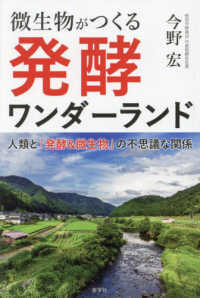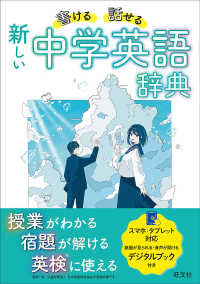出版社内容情報
占星術、超能力研究、東洋医学、創造科学・・・・・・これらはなぜ「疑似科学」と言われる
のだろうか。はたして疑似科学と科学の間に線は引けるのだろうか。科学のようで科学でない
疑似科学を考察することを通して、「科学とは何か」を解き明かしてゆくユニークで真っ当な
科学哲学入門。
目次:
序 章
第1章 科学の正しいやり方とは?
――創造科学論争を通して
第2章 科学は昔から科学だったのか?
――占星術と天文学
第3章 目に見えないものも存在するのか?
――超能力研究から
第4章 科学と疑似科学と社会
――代替医療を題材に
第5章 「程度」の問題
――信じやすさの心理学から確率・統計的思考法へ
終 章
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
70
疑似科学を扱うことで、科学との違いと科学とは何かを論じる科学哲学入門。創造科学(聖書の記述が正しい前提がある疑似科学)と進化論の論争や天文学と占星術、超能力を扱う超心理学、代替治療ホメオパシーなど。ほかの科学哲学の入門書で難しく感じたところがよくわかった。特に、科学の実在論と反実在論(目に見えないものは、本当にあるのか無いのか)は他の本でよくわからなかったのだが、超能力の考察で非常に納得がいった。奥行きのある議論を分かりやすく考察解説してあり実におすすめ。2018/03/15
井の中の蛙
12
なぜこれまでこの本を読んでいなかったのか分からないぐらい面白かった。高校倫理で扱ったポパーやクーンに留まらない科学哲学の広範な思想について事例を挙げながら解説されていた。ベイズ主義についてもっと詳しく学びたいと思った。2024/11/12
かやは
12
疑似科学を使って科学哲学を説明している一冊。最終的な指針は線を引かずに「線引き問題」を解決することにある。哲学は答えを出す学問ではない。考え、理解することを目的とする。「現実」を検証することはほぼ不可能に近く、科学的という言葉は必ずしも絶対的ではないと改めて知った。物事を判断するためにどれだけの言葉を尽くしても足りないという事実を噛み締める。難解な部分もあったけれど、全体的にはかなりわかりやすく書かれている。2023/08/15
白義
12
科学哲学最初の教科書としてベスト。リーダビリティと濃さ、穏健さと刺激がまさにちょうどいいバランス。占星術や超心理学などきわどい事例から科学と科学じゃないものの境界線を考え、安直な相対主義を退けつつも、確率を考慮するベイズ主義の考えから別に境界線はなく程度問題だし、そうだとしても科学は困らない、という結論を導き出している。反証主義や合理的進歩論、実在論と道具主義などといった論点をあっさりした解説に済まさず丹念に検証しているのもいい。科学的思考を学ぶならこの著者と戸田山和久の本は特にオススメ2012/01/23
zirou1984
8
これは面白い。「科学と擬似科学の間に明確な線引きは可能だろうか?」という問いを中心に置きながら、20世紀における科学哲学の論点を整理していくことで科学的なものの在り方がどの様に変遷していったのかを理解する事ができる。また各章の冒頭に創造科学や占星術、代替医療といった疑似科学の事例と歴史について触れられており、常に具体例との対比で考えさせる構成のおかげで教科書的な退屈さは全く感じられなかった。あとがきで述べられている「健全な懐疑主義」、まっとうに疑う姿勢とその技術の必要性については心の底から同意したい。2012/11/26