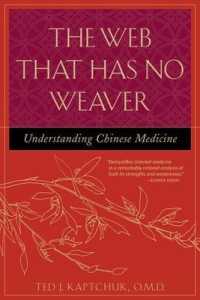出版社内容情報
シリーズ累計13万部超!
SB新書『自閉症スペクトラム』(2013年3月刊)
SB新書『発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち』(2018年12月刊)
臨床経験30年以上の専門医が現場から伝えたい"本当のこと"
「グレーとは白ではなくて薄い黒」
「『友達と仲良く』と言ってはいけない」
「『せめてこれくらい』はNGワード」
「宿題は百害あって一利なし」
など、「発達障害」当事者の親にしてみるとぐっと心に刺さることを笑顔でおっしゃる本田先生。
ただし、その解説をうかがうと非常に腑に落ちて、合理的で、子どもの発達に不安や悩みを抱える親御さんには、目からウロコの本になると思います。
親や支援者たちの認識をコペルニクス的に変える! 新たな知見を授け、支援の意味に気づかせる一冊です。(編集担当)。
内容説明
ほかの子とは成長のペースが違う発達障害の子どもたち。定型発達の子どもに近づける必要はありませんし、その子なりのペースで大人になっていけばいいのです。育て方のポイントは3つ、「多数派に合わせない」「平均値に合わせない」「友達に合わせない」―本書では、幼児期から思春期にさしかかる時期までの育て方を解説します。臨床経験30年以上の児童精神科医が伝える「発達障害の子育て」の決定版!
目次
第1章 発達障害の子育てを考える8つのクイズ(小さなイチゴをもいだ子にどう声をかける?;電灯のスイッチをいたずらする子にどう声をかける? ほか)
第2章 あらためて、発達障害とは?(「発達障害」とは数種類の障害の総称;発達障害には「重複」や「強弱」がある ほか)
第3章 発達障害の子のほめ方・叱り方(発達障害の子のほめ方:キーワードは「下心」;発達障害の子の叱り方:キーワードは「本気」 ほか)
第4章 発達障害の子の暮らし方 場面別のポイント(生活スキル編;対人関係・勉強・学校編)
第5章 あらためて、発達障害の子の育て方とは?(「発達障害の子の育て方」とは;「早期発見・早期療育」が大事? ほか)
著者等紹介
本田秀夫[ホンダヒデオ]
信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長、特定非営利活動法人ネスト・ジャパン代表理事。精神科医。医学博士。1988年、東京大学医学部医学科を卒業。東京大学附属病院、国立精神・神経センター武蔵病院を経て、横浜市総合リハビリテーションセンターで20年にわたり発達障害の臨床と研究に従事。発達障害に関する学術論文多数。英国で発行されている自閉症の学術専門誌『Autism』の編集委員。2011年、山梨県立こころの発達総合支援センターの初代所長に就任。2014年、信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部部長。2018年より現職。日本自閉症スペクトラム学会常任理事、日本児童青年精神医学会理事、日本自閉症協会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。