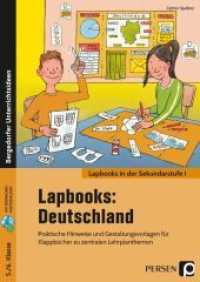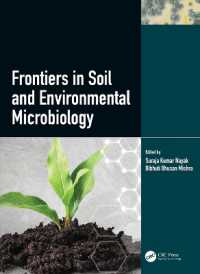出版社内容情報
GitHub Copilotを実装した著者がLLMとプロンプトエンジニアリングの仕組みを解説!
LLMのポテンシャルを最大限に引き出し、期待通りの精度の高いアウトプットを引き出すためには、LLMの能力や特性を正しく評価、把握し、綿密な設計に基づいたプロンプトを組み立てることが必要です。本書では、まずLLMを理解することから始め、その上で、プロンプトにはどんなことを組み込み、どのような構造にすべきか、本来の意味での「プロンプトエンジニアリング」を行う方法を説明しています。著者たちはGitHub Copilotの開発者であり、その実装過程で得られた貴重な知見や、評価手法、設計上の判断など、通常は表に出てこない開発の裏側も詳しく解説されています。AIアプリケーション開発の実際を知りたい開発者はもちろん、生成AIの可能性と限界を理解したいユーザーにとっても、示唆に富む内容となっています。
内容説明
LLMのポテンシャルを最大限活かし、期待通りの精度の高いアウトプットを引き出すためには、LLMの能力や特性を正しく評価、把握し、綿密な設計に基づいたプロンプトを組み立てることが必要です。本書では、まずLLMを理解することから始め、その上で、プロンプトにはどんなことを組み込み、どのような構造にすべきか、本来の意味での「プロンプトエンジニアリング」を行う方法を説明しています。著者たちはGitHub Copilotの開発者であり、その実装過程で得られた貴重な知見や、評価手法、設計上の判断など、通常は表に出てこない開発の裏側も詳しく解説されています。AIアプリケーション開発の実際を知りたい開発者はもちろん、生成AIの可能性と限界を理解したいユーザーにとっても、示唆に富む内容となっています。
目次
1部 基礎(プロンプトエンジニアリングの世界;LLMを理解する;チャット形式への移行;LLMアプリケーションの設計)
2部 中心的なテクニック(プロンプトのコンテンツ;プロンプトの組み立て;モデルの制御)
3部 プロンプト作成のエキスパート(会話型エージェント;LLMワークフロー;LLMアプリケーションの評価;未来を見据えて)
著者等紹介
服部佑樹[ハットリユウキ]
マイクロソフトでAzureのソリューションアーキテクトとしてクラウドとDevOpsの推進に従事したのち、現在はGitHubのシニアアーキテクトとして、GitHub Copilotの日本国内での普及を牽引。InnerSource Commons財団のプレジデントを務め、オープンソース文化およびプラクティスの企業内導入の世界的な発展に貢献している。情報処理推進機構(IPA)においてオープンソース推進の専門委員を務める
佐藤直生[サトウナオキ]
日本オラクル株式会社における、Java EEアプリケーションサーバやミドルウェアのソフトウェアエンジニア/テクノロジーエバンジェリストとしての経験を経て、現在はMicrosoft Corporationで、パブリッククラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」のプリンシパルソフトウェアエンジニアとして活動
Berryman,John[BERRYMAN,JOHN] [Berryman,John]
ジョン・ベリーマン。LLMアプリケーション開発を専門とするArcturus Labsの創設者兼主任コンサルタント。その専門性で、企業が高度なAIテクノロジーの能力を活用できるように支援する。GitHub Copilotの初期のエンジニアとして、補完機能とチャット機能の開発に貢献。AI支援コーディングツールの最前線で活躍する。Copilotに関わる前は、米国特許庁の次世代検索システムの開発の支援、Eventbriteの検索と推薦システムの構築、GitHubのコード検索インフラストラクチャへの貢献など検索エンジニアとして多様なキャリアを築く
Ziegler,Albert[ZIEGLER,ALBERT] [Ziegler,Albert]
アルバート・ジーグラー。LLMアプリケーションが主流となるずっと以前からAI駆動システムを設計している。GitHub Copilotの創設エンジニアとして、そのプロンプトエンジニアリングシステムを設計し、AI搭載ツールと「Copilot」アプリケーションの波にインスピレーションを与え、開発者支援とLLMアプリケーションの未来の形成に貢献した。現在はAIサイバーセキュリティ企業、XBOWのAI責任者として、AI技術の限界を広げ続けている。XBOWでは大規模言語モデルと鼓先端のセキュリティアプリケーションを融合させ、明日のデジタル世界の安全を確保する取り組みを主導している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
iwtn_
yu-ya4
monotony
レスペピック
しんたろ
-

- 電子書籍
- ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作…
-

- 電子書籍
- お局様は腐女子様!?~3次元年下男子は…