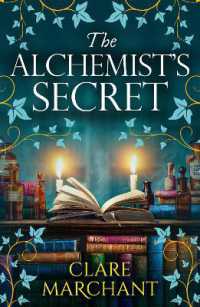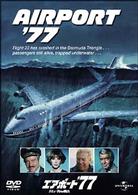- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
1テーマ5分で読めて、すぐに生かせる子ども理解術。
目次
第1章 こうすればうまくいく―発達につまずきがある子とのシンプルな関わり方(話を聞けない、指示が入らない子;切り替えが難しい子 ほか)
第2章 こうすれば輝く―子どもの効果的な伸ばし方(「ムカつく」や「ウザい」が口癖の子;忘れ物が多い子・提出物をなかなか出せない子 ほか)
第3章 子どもたちの心に届く―ほめ方・叱り方・認め方(「お試し行動」に振り回されないために;子どもの心に響くほめ方 ほか)
第4章 大人も自分を磨き続けよう―子ども理解のさらなる深め方(子どものつまずきを読み解く「知識」と「洞察力」を;子ども理解に欠かせない「四つの軸」 ほか)
第5章 教育の本質―いかに自分のあり方を見つめ直すか(子どもはルールよりも「ラポール」に従う;教師としての軸・枠・型・幅をもつ ほか)
著者等紹介
川上康則[カワカミヤスノリ]
1974年、東京都生まれ。東京都立矢口特別支援学校主任教諭。公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー。立教大学卒業、筑波大学大学院修了。肢体不自由、知的障害、自閉症、ADHDやLDなどの障害のある子に対する教育実践を積むとともに、地域の学校現場や保護者などからの「ちょっと気になる子」への相談支援にも携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 悪女の私がヒロインになります【タテヨミ…