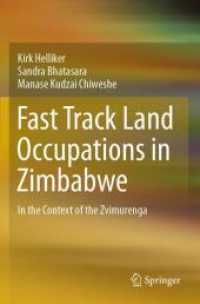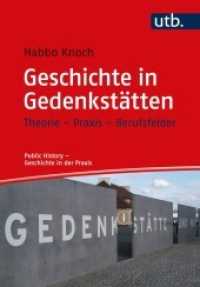出版社内容情報
学校の学びから大脱走する子ども・若者たちが、どうしたら学びをとりもどすことができるか。自分と世界をつくりかえる学び方を学ぶことから、自分の学びのつくり方を学ぶ。
プロローグ 学びの再生──着地するために
学びのなかの戦争と平和
I 学びからの大脱走(エクソダス)がはじまった
もう学力という概念では考えない
1 岐路に立つ学校と社会
2 自らの学びをつくる力をどう育てるか
授業に出てこない生徒諸君に
3 流れる水が河をつくる
4 学校リストラの時代とどう向きあうか
学ぶこと・働くことの実践記録
──読書ノート・池野高理著『さて、メシをどう食うか』
II 学びの再生──離陸するために
1 世界と出会う若者たち──大学のある一般教養講座の試み
2 スカラベの世界
III 自分の学びを創る──講座「学校と文化」
1 大学の窓から見た学びの風景
2 学びと文化──98年10月20日
3 動詞「学ぶ」について──「学びと文化」98年10月27日
4 動詞「つくる」と「壊す」について──「学びと文化」98年11月17日
5 額ぶちのなかの行為(「学ぶ」再説)──「学びと文化」98年12月1日
6 動詞「読む」をめぐって──「学びと文化」98年12月8日
7 もう一つの時間のまえで──「学びと文化」99年1月19日
エピローグ 人は考える「能力」があるから
オビから
学校文化が誇る「知性」や「能力」の切れ味は、
若者が振りまわすナイフの切れ味と同じだ。
「ナイフ=自分」という自己喪失(=非人間化)からどのように脱出するか。
知識というのは属人的なものです。それは私の知識であったり、あなたの知識であって、つまり、私やあなたという固有の人格と結びついた知識なのであって、だれのものでもない、人間に超越した客体ではないのです。学習とは、そうした「自分の知識」をつくりだしていく営みです。モノやコトとの、そして本との交渉をとおして自分の世界を構築していく、すぐれて構成的な行為です。権威づけられた知識を外からとりこんで空洞の自我を満たしていく、そういう受け身の行為ではありえないはずなのです。
内容説明
学校文化が誇る「知性」や「能力」の切れ味は、若者が振りまわすナイフの切れ味と同じだ。「ナイフ=自分」という自己喪失(=非人間化)からどのように脱出するか。
目次
プロローグ 学びの再生―着地するために
1 学びからの大脱走がはじまった(岐路に立つ学校と社会;自らの学びをつくる力をどう育てるか;流れる水が河をつくる;学校リストラの時代とどう向きあうか)
2 学びの再生―離陸するために(世界と出会う若者たち―大学のある一般教養講座の試み;スカラベの世界)
3 自分の学びを創る―講座「学校と文化」(大学の窓から見た学びの風景;学びと文化―98年10月20日;動詞「学ぶ」について―「学びと文化」98年10月27日 ほか)
エピローグ 人は考える「能力」があるから考えるのではない
著者等紹介
里見実[サトミミノル]
教育学専攻。国学院大学教員、自由の森学園協力研究者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。