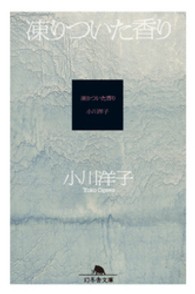目次
第1章 絵をやりたい―〇~二十四歳(明治十三~三十七年)
第2章 模索の日々―二十五~五十八歳(明治三十八~昭和十三年)
第3章 モリカズ様式の確立―五十九~九十七歳(昭和十四~五十二年)
著者等紹介
池田良平[イケダリョウヘイ]
山形県生まれ。天童市美術館館長・学芸員
蔵屋美香[クラヤミカ]
千葉県生まれ。東京国立近代美術館企画課長。企画担当した主な展覧会に「ぬぐ絵画―日本のヌード1880‐1945」(2011~12年、第24回倫雅美術奨励賞)、第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館キュレーターも担当(2013年、アーティスト:田中功起、特別表彰)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
80
明治32年1899年守一19歳の時に描いたデッサン「ワサビに人参」から昭和51年1976年油彩画の最後の作品「アゲ羽蝶」まで、70年以上に渡り描いてきた変遷の概要がわかる。さまざまな実践を通じて、いわゆる「モリカズ様式」と呼ばれる輪郭線を明瞭に、形態は簡潔に、色彩ははっきりと描くようになった形の完成は、75歳の時だという。配色を考え、影を描かない方法は、1900年初頭のマティスの影響もあったらしい。東京美術学校(現在東京藝術大学)で同期の青木繁とは馬が合い尊重し合っていた。薄い本だが、多くの絵が載って→2020/08/23
booklight
31
自分の画風を掴んだのが75歳かぁ。芸大を卒業してすぐの自画像もいい。しかしこの後に模索の時代が続く。途中の作品もいいのだけれど、やはり晩年のモリカズ様式が確立してからが頭一つ抜けている。シンプルだが今までの模索が背後に見え隠れするので深みがある。「アゲ葉蝶」を見ていても妙な悲しさと透徹した眼差しと少しの喜びを感じる。轢死体をスケッチしてしまうような、死んだ息子のために何か形を残そうとして絵を描き始めたら「絵」を描いてしまうようなどこか熱く冷めた部分を、晩年人に魅せられる形にできたのはよかったのだろう。2022/09/18
とよぽん
23
熊谷守一の生涯と作品を駆け足でたどった。芸術家の生活を支える人というのは、必須の存在なのか? 現代の芸術家の中には、大学教授をしていたり自分の名を付けた美術館を経営(?)していたり、そこそこリッチな人がいるけれど。守一さんは赤貧というほど貧しい時期があったようで、友人や家族が生活の支えとなっていた。70歳以降に確立された画風・・・色、画面構成、視点、線に、これが究極の到達点なのだと感じた。2019/09/10
サラダボウル
18
画家は晩年、庭の花や昆虫を描いた。どれ程見つめたか、と感じる絵。シンプルなのに紫陽花を、アゲハ蝶を、千日紅をこちらの脳裏に鮮明に浮かび上がらせる。不思議だなぁ。千日紅は最近名前を知ったので(それまで勝手に背高赤ボンボンと呼んでいた)、なんだか感慨深かった。本物の絵を見たいなぁ。2022/11/13
遠い日
12
画風が確立されたのは70歳を過ぎてからだとか。わたしが好きな画風は晩年のものであったと知る。単純で大胆な構図と色。図案化されたものの形。愛らしく、しかし、どんなものもここに在ると真っ当な主張をしている感じ。好きです、守一。2018/03/02
-
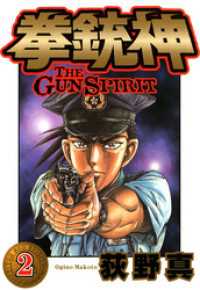
- 電子書籍
- 拳銃神 第2巻