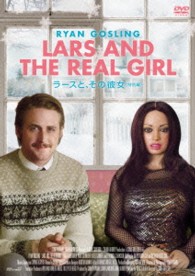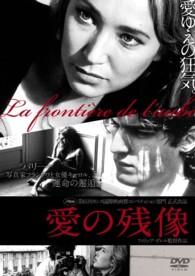内容説明
本来、姿形をもたない神々は、どのようにあらわされてきたのか―。神像の歴史をたどり、日本人にとっての「聖なるものの姿」を明らかにする。長らく神域の内部で秘匿され、「再発見」された貴重な神々の御像を紹介。僧形神や神道曼荼羅、習合神像を通じて、神仏習合のあり方を読み解く。最古期の木彫像から近世・近代の御影まで一五〇点を超える神像を収録。
目次
第1章 僧侶姿の神々(仏という神の登場;仏に秘められた神性 ほか)
第2章 ヒコ神とヒメ神(神像ならではの霊威;霊木からあらわれた神 ほか)
第3章 共存する神と仏(聖なる山と神々の浄土―春日1;神々の本地仏が宿る神域―春日2 ほか)
第4章 神と仏が習合したかたち(あらわれた天照大神の異相;除疫神となったスサノオの本地 ほか)
第5章 庶民に愛された神々(庶民も信奉した三社の託宣;三六〇日、交代で守護する神々 ほか)
著者等紹介
三橋健[ミツハシタケシ]
1939年、石川県金沢市生まれ。國學院大學文学部文学科卒業、同大学院文学研究科神道学専攻博士課程単位取得退学。博士(神道学)。國學院大學神道文化学部および大学院教授を経て、同大学院客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
9
日本の神サマはもともと姿形がないため、いろいろな自然物を依代として信仰の対象となっていましたので、日本に伝来してきた仏や菩薩とコラボして権現や垂迹神になったり、インド神話の神サマとコラボして七福神になったりすることはお手のものだったようです。七福神と言えば、その解説で「ゆるキャラの原型」と書いてあり、なるほどと思いました。昔から日本人はゆるキャラが好きだったんですね。この本を読んで、バラエティーに富んだ日本の神像たちに会いに行きたくなりました。2012/11/10
nizimasu
3
これまた神道の神様が神仏習合の過程で様々な像として、依代となっていく歴史が解説がわかりやすく読めた。この本はどちらかというと美術より、より歴史的な神道の変遷みたいな背景もうかがえて、より神道世界を味わうにはうってつけのテキストでした2013/01/23