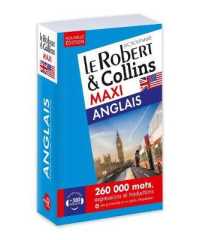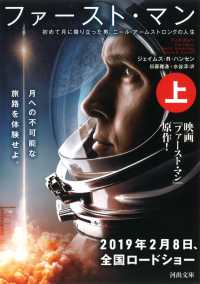内容説明
2度にわたるバルカン戦争(1912‐13年)に戦争特派員としてバルカンに赴いたトロツキーは、みずから面会したバルカン諸国の政治家、将校、兵士、負傷者、捕虜たちの口をつうじて、戦争サディズム、戦場での兵士の心理、短期間のうちに殺人鬼と化す兵士の堕落、戦争後のコレラの蔓延…、そして、こんにちなおバルカン問題の根底にある民族問題解決の道筋を語る。
目次
第1部 戦争の入口で(バルカン問題;バルカン諸国と社会主義;ブルガリア民主主義の謎)
第2部 戦争(戦時下のセルビア;戦時下のブルガリア第一期―トルコに対する同盟;戦争参加者の物語 ほか)
第3部 戦後のルーマニア(最初の印象;ルーマニア・ブルガリア関係;改革をめぐって ほか)
著者等紹介
清水昭雄[シミズアキオ]
1949年東京生まれ。1983年一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得。横浜国立大学、一橋大学などの非常勤講師を経て、現在、志学館大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
傘緑
43
「バルカン戦争の根底には、この驚くべき半島――自然の恵みはたいそう豊かではあるが、歴史によってひどく傷つけられた半島――の民族的、経済的、国家的矛盾に根差した深い原因が存在する」マイテルの官能小説の方ではないw革命家トロツキー(トロッキに非ずw)が第一次・二次バルカン戦争の従軍記者時代に書いた、『カタロニア讃歌』にも比肩しうる戦争ルポの傑作中の傑作。過去から現在まで続くバルカンの混沌とした状況が革命家トロツキーの目と名文を通して克明に記されている。「民族的、国家的カオスと血なまぐさい混乱からの唯一の(→)2017/05/19
傘緑
39
「ヴィクトル・アドラーは、オーストリアの国家体制を、怠慢さによって和らげられた絶対主義と定義した…オーストリアの愛すべきだらしなさ…さまざまな言語と雑多な人種のるつぼ…一知半解の言葉、説明の身振り、誤解、互いにただ半分だけ理解しあうことに慣れてしまった人々のやさしい微笑み。オーストリア=ハンガリー・バルカン・インターナショナル!」(バルカンへの)『旅の途中』と題された屈指の名文。J・ロート『皇帝の胸像』にも書かれた、民族自決という不寛容の精神によって崩壊した、ただ座って息をしているだけの、理想的な連邦体制2017/05/22
はる
10
ウクライナ・ヤノーフカ村の中層農民の家を故郷にするユダヤ人トロツキーが歩いて見て聞いてレポートした民族の坩堝バルカン半島からのレポート。ロマノフ王朝を東に、ハプスブルク=フランツ・ヨーゼフを西に、南にオスマン・トルコの拮抗の中に在って、ドイツ語ハンガリー語ブルガリア語ルーマニア語セルビア語ペルシア語アラビア語ギリシャ語フランス語ポーランド語ドイツ語…(書けば切りがないが)を日常語とする文化を内在する人々の住むバルカンが提出している民族と国家の問題を未来的展望から分析評価している。2022/11/16
するたん
1
のちにソ連の革命家として史上に名を残すことになるトロツキーが新聞記者だったころの、第一次・第二次バルカン戦争のレポート・論文集。欧州帝国主義諸国の思惑によって成立した「正統性のない」バルカン諸国が結局は帝国主義的国策を執ってバルカン戦争に進むことへの失望、戦争の愚かさを臨場感あふれるレポートで追うことが出来る。2019/02/14