出版社内容情報
利用者だけが知っている、安心して、納得して婦人科にかかるコツ。
患者としての体験と、患者サポートグループの活動経験から生まれた、すべての女性に贈るとっておきのアドバイス。
【各氏絶讃】
●堀口雅子氏(虎の門病院産婦人科医師・性と健康を考える女性専門家の会)=こんな本を待っていた!
●斎藤綾子氏(作家)=二人は婦人科というパンドラの匣を開けた。希望を手に入れるために。
【書評再録】
●朝日新聞「家庭欄」(2001年7月11日)=患者が安心して納得できる医療を受けるための助言をまとめた。患者の疑問や不安に2人が答える形で構成されている。私の初診体験、私の病院選び・医師選びといったテーマの2人の対談も収録。性暴力被害にあった女性のための医療、インターネットでの情報収集のコツなどのコラムもある。巻末には、専門用語の解説や女性医師のリストを掲載した。
●読売新聞「家庭とくらし欄」(2001年7月8日)=心配な症状があっても、婦人科には行きづらいもの。患者から見た医療情報の少ない中で、体験を交えたアドバイスが高い敷居を越える心強い味方になりそうだ。医師の心ない言動にとまどい、傷ついた体験が今回の本につながったという。
●毎日新聞「家庭欄」(2001年7月14日)=「なぜ婦人科にかかりにくいの?」
そんな疑問に答えるアドバイス集。婦人科医療について利用者が書いたガイドブック。
「総合病院や大学病院で女性医師を望むことはできるか」「痛みを伴う検査にはどんなものがあるのか」「早く手術したほうがいいと言われたが、このまま手術を受けていいのか」など、28の質問に丁寧に説明。「傷つき体験」などについての対談もある。
●新潟日報評(2001年7月16日)ほか・時事通信全国配信記事=内容は28項目のQ&Aが中心。質問は2人の活動を通じて得た生の声を反映させた。受診時の服装、問診表の書き方など入口の問題から、医者の説明への対応法や、診察後、別の医者に意見を聴くセカンドオピニオンの求め方まで、詳細にわたる。また、難しい専門用語は極力使わず、婦人科初心者にも分かりやすくなるよう配慮を加えた。
婦人科体験を通じ、二人は医者との間に「暗くて深い河が流れている」とつくづく感じる。隣に声が筒抜けの診察室や、出産で歓声が上がる横での治療、内診を無断で研修生に見学させる大学病院など、医療側の無神経な対応による「傷つき体験」が同書にあふれている。
●朝日新聞評(2001年7月27日)【苦手な「婦人科」活用したい―利用者の立場で出版】
受診のための準備から、自分にあった病院探しまで、体験に基づいたアドバイスがまとめられている。
●サンデー毎日評(2001年8月12日号)=患者としての体験、患者サポートグループの活動体験から生まれた、利用者の立場に立つ「徹底ガイド」。巻末資料も役に立つ。こんな本が、どうしていままでなかったのだろう。
【読者の声】
●女性=本当に、書名のとおり、婦人科にかかりにくいと思っている人は、私を含め、多いと思う。それに応えてくださる本で、婦人科の医師に読んでほしいと思います。私の担当の医師にも読んでほしい。
●女性=私は先月に婦人科の手術を受けたばかりです。また、医療関係の仕事をしている中で、今回の本は、納得いく本と同感することばかりです。読みやすい本でした。この本を、婦人科の医師やナースに、ぜひ、読んでほしいと願います。もっともっと女性心理を理解してほしいですよね。
●女性(60歳)=とてもよい本だと思いました。私も先生にお聞きするのは苦手ですので、看護婦さんと仲良くなって何でも教えていただいています。
【内容紹介】●本書「はじめに」より
婦人科医の書いた婦人科についての本は数多く出版されていますが、肝心の知りたいことが書いてなかったり、「(患者からすると)これは違うでしょう……」と思うことがかなりあります。
例えば、こんな文章を読んだときです。
「あなたにとって、性器はアカの他人になど見られたくない特別な場所かもしれません。でも、婦人科の医師にとって、性器は診察するカラダの一部でしかありません。眼科の医師が目を見るように、性器を見る。それだけのことです」
「……こうした姿勢で診察を受けることは羞恥心が働いて、誰もができれば避けたいと思いがちです。しかし、内診は歯医者さんで口をあけるのと同じことなのです。決して恥ずかしいものではありません」
「ドクターは毎日おおぜいの患者さんに接しているし、何よりも病気を主体として見ていますから、内診も単に診断手段として行っているものです。ですからあまり恥ずかしがらず、割り切って受診されたほうがいいと思います」
女性たちの婦人科受診への抵抗感をやわらげようとする、書き手の医師たちの優しさや思いやりがひしひしと伝わってきます。でも、私たちが内診台で開くのは、まぶたでも、くちびるでもない。
医師が恥ずかしくなくても、私たちは恥ずかしい。医師は慣れっこでも、私たちは慣れていない。医師や看護婦が、人によっては「性器だけ」を見ていて、その持ち主に人格があることを、うっかり忘れてしまうことが問題だったりするのです。まさに、そのからだの部位や、立場の「違い」が問題なんです。そんなわけで、「これまで、あまり語られてこなかった患者からの声が、ぜひ必要だね」というのが作り手たちの共通の思いです。
私たちふたりは、相談活動などを通じて、婦人科医療にはぐれたり、適切な医師にたどりつけていないために、苦痛を長引かせたり、病気を進行させてしまった人たちに数多く出会っています。一方、不安をあおって、必要もないのに、医療に追いこむようなことはしたくありません。そのため、私たちの合言葉は、「必要なときに、婦人科にかかる機会を逃さないために」。そして、どうせかかるなら、「あなたが、安心・納得できる治療が受けられるように」。
利用者がネットワークするなかで、見えてきたことがあります。婦人科は、医師や病院によって、診断や治療法にかなりのばらつきがあること。不十分な説明しか受けられず、医師とのコミュニケーション不足に悩んでいる人が山ほどいること。外来での医師との会話が外にもれ聞こえたり、患者に無断で研修生が内診の見学をすることが当たり前になっていたりと、プライバシーが守られていないこと。カルテの開示など、情報公開が遅れていること。良性疾患、悪性疾患を問わず、必要なメンタルケアや、その人に合った治療を選ぶためのサポートが不足していること。医師によっては、診察を通じて、女性である患者さんの生き方、人生設計にまで、口を差しはさんでくること。検査や治療には限界があるのに、患者にそれが知られていないため、医療への幻想が独り歩きしがちなこと。がん検診によって引き起こされる被害のこと……。ほかの医療の分野でも事情は似たりよったりのところがありますが、婦人科は特に情報が少ないので、それが見えにくくなっています。
この本が、みんなが感じていたことや、知りたいことをオープンにしていく、ひとつの突破口になりますように。わたなべさんも私も、婦人科にかかるのに最初は手探りで、いっぱい失敗を重ねてきたので、これからかかる人や、かかりながら悩んでいる人たちが、「できるだけ失敗をくり返さないですむように」という切ない気持ちで、自分たちの恥ずかしい経験も、紹介しています。
【主要目次】
対談1・私の初診体験
内容説明
患者としての体験と患者サポートグループの活動経験から生まれたすべての女性に贈る、とっておきのアドバイス。
目次
仕事で忙しくて受診の時間がとれません。何かよい方法は?
電話やeメールでの相談を上手に利用するコツはありますか?
総合病院や大学病院で女性医師を希望することはできますか?
月経中に受診してもかまいませんか?
受診するときはどんな服装でいくと便利でしょうか?
受診するときに持っていったほうがいいものはありますか?
問診表の書き方のコツはありますか?また性体験など、ほんとうのことを書かないといけませんか?
月経血の量はどうやって判断したらいいのでしょう?
痛みをともなう検査にはどんなものがあるのですか?
内診は必ず受けないといけないものですか?〔ほか〕
著者等紹介
まつばらけい[マツバラケイ]
1960年生まれ。食と健康の専門誌の編集者を経て、フリーライター。アレルギーの患者会の事務局を7年つとめる。健康法はヨーガと、リンパ浮腫治療のための水中療法。2000年2月に子宮がんの手術を受け、同年5月に「子宮・卵巣がんのサポートグループあいあい」を発足。その後、がん術後の後遺症の深刻さに衝撃を受け、「リンパ浮腫にとりくむ会りんりん」を発足。わかちあいのミーティングや講演会、体験交流会、電話相談など、幅広い活動を行っている
わたなべゆうこ[ワタナベユウコ]
1954年生まれ。フリーライター。主な執筆分野は医療、女性問題、子育てなど。1985年に子宮筋腫の診断。1989年に子宮外妊娠とその後の絨毛がんの疑いにより1カ月の入院生活。1993年、子宮腺筋症の診断により子宮全摘手術。1994年、友人と2人で呼びかけ人となり、子宮筋腫・内膜症体験者の会「たんぽぽ」を発足。2001年4月「たんぽぽ」卒業
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切…
-

- 電子書籍
- 悪魔はそこに居る 1巻 まんが職人スタ…
-

- 電子書籍
- マーディスト ―死刑囚・風見多鶴―(ノ…
-
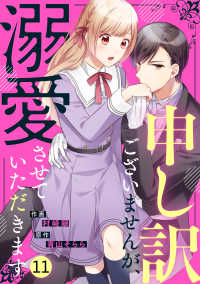
- 電子書籍
- noicomi 申し訳ございませんが、…
-
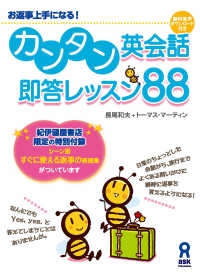
- 電子書籍
- カンタン英会話 即答レッスン88



