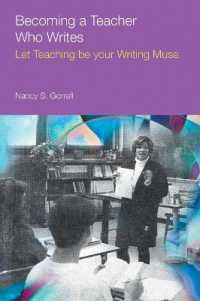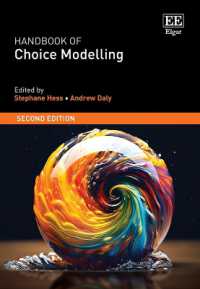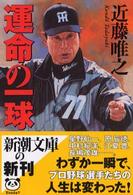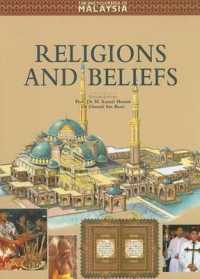出版社内容情報
日本に巣くう病巣を鮮やかに浮き彫りにする書。
水質調査をはじめとする継続的で着実な調査。リーダーを議会に送り込み、行政を効果的に動かす科学的な調査にもとづく力量。それでも超えられない政治・経済の利権構造……行政にかかわる住民運動のモデルケースとして全国的に注目を集める活動リポート。
【書評再録】
●朝日新聞評(2000年10月22日)=経済効率を優先して上水道を建設し、地下水環境を悪化させた行政に対し、保全活動をすすめる会の活動を詳述。
●日本農業新聞評(2000年10月2日)=地域の大切な水を守ろうとする情熱はすごい。生活に根ざしたその手法は、学ぶべき多くのものがあり、全国の運動に勇気を与えてくれそうだ。
●山科鳥研News評(2000年10月号)=この本は水問題のみならず公共事業と自然環境問題を考える上で、多くの議論を巻き起こすに違いない。
【内容紹介】本書「はしがき……津郷勇」より
山紫水明の地、名水の町として全国的に知名度の高い福井県大野市は、往時には町のいたるところに豊富、清澄な湧水に恵まれ、文字通り名水の町に相応しい風情を醸し、清澄な湧水のみに棲み、水草に造巣する淡水小魚「イトヨ」の、わが国における数少ない貴重な生息地としても知られ、湧水と歴史的な町並みが県内外の多くの人々から親しまれている。
ところが、近年、市民生活様態の様変わり、用水型産業構造の変化、涵養水源付近での耕地基盤整備の進捗、不浸透地表の増加、公私諸施設での雪対策用水の飛躍的な使用量増加、利便追求型市民生活、無対策的な産業用水の大量使用に伴い、井戸水の慢性的な枯渇で市民生活に不便を来し、湧水の枯渇に、有機塩素溶剤による汚染の問題が加わって、大野の水問題は一般市民に地下水を守る運動としての意識の高揚を促していく。
しかしながら、大野の水問題は、その後も混沌とし、行政からも市民サイドからも科学的・技術的背景をもった、真に最適かつ具体的な解決策が出ないまま、上下水道の計画が進んできている。
市民参加のためには、市民サイドの知識を専門的レベルまで向上させることと、特に、行政サイドでの情報公開、リーダーシップの発揮、問題解決へ向けた協調的姿勢、努力が肝要となる。全国に先駆けて、進歩的な市民参加型の活動を展開していただきたいと願っている。問題に対する利害・相互の立場を個々の思いに限定せず、真の専門的・学術的立場に立脚した解決策へ向けた全市域向きベクトルを持って欲しい。
【内容紹介】本書「あとがき……柴崎達雄」より
「大野の水問題は、日本の水問題のすべてを凝縮している」
その直感は大野盆地の地形・地質からくる、自然科学的なセンスに大半はもとづいていた。しかし、この著作を読まれればお分かりのように、大野の水問題は自然科学的な視点をこえて、日本の水政策のあり方、さらには地方自治のあり方、究極的には、日本の政治の本質までに論がすすめられている。つまり、現在、私たちが抱えこんでいる政治経済的な問題までもが、大野という一地方都市の水問題に凝縮しているのである。
とくに、過去長年にわたって実施されてきた「公共事業」のツケが、高い水道料金として住民に降り注いでくる昨今の行政システムの矛盾、またそれをおしすすめてきた古い政治・行政・業界の癒着の実情を、これまで具体的にあばきだした記録は、あまり前例がないと思われる。とくに、主婦という感覚から出発した運動が、日本の古い政治体質の深層部をえぐりだしたことに、一種の感銘さえ覚えるほどである。
もちろん、この事態をするどくえぐりだしたのは、野田さんを始めとする「水を考える会」の人たちの、四半世紀におよぶ絶え間ない活動によるものであることは、多言を要しないであろう。いろいろな難題が起こったとき、まず現地調査によって、事実を確かめながら相手を論破していくやり方は、環境問題を解明する基本的な手法である。また疑問に思ったことは、自ら実験台になってデータを求め、そのためには多大の苦労も辞さないという、野田さんたちの積極的な行動は、私たちにとっても、大きな反省と再挑戦する気概を与えてくれたことに感謝したい。また、現在大学などの研究室に閉じこもり、環境科学を専門にしていると自称している研究者の人たちには、ぜひ学んで欲しいものである。
【主要目次】
▲▲第1章 手おくれの地下水対策
1.新聞の警告記事
2.地下水のまち大野市と三八豪雪
3.地下水融雪と井戸枯れ
4.実態調査で地下水保全条例をせまる
5.つまずいた上水道政策
6.県の融雪再開で、議会出馬の決意
▲▲第2章 議会へ出て知る地方政治の実情
1.女のあんたにゃ任せられない
2.公共事業で殺された大野の地下水
3.地方政治をゆがめる補助金行政
4.行政の上水道信仰
5.ダム計画と産業政策
6.人間的良心をしぼませるお役所カラー
▲▲第3章 トヨタ財団の助成と市民の調査活動
1.専門家を探し求めて
2.大野盆地の湧水調査
3.大野盆地の河川調査
4.湧水地帯に集中している繊維工場
5.湿地埋立ての駅東都市計画
6.調査で学んだ自然への畏敬
7.「おいしい水は宝もの」の出版
▲▲第4章 名水シンポジウム開催と国の水政策転換
1.名水シンポジウム大野市への道のり
2.水環境シンポジウムを水観光にとりちがえた市長
3.浮かびあがった地下水の流れ
4.シロウト・サイエンスに歓声
5.もう一つのシンポジウム「水の会」の前夜祭
6.大会は地下水保全の核心にせまれず
7.国土庁、水政策に女性の視点導入
8.エイボン大賞の受賞
▲▲第5章 地下水汚染と専門家の支援
1.シリコンバレーからの警鐘
2.昭和62年、有機溶剤の汚染発見
3.情報かくしで広がるパニック
4.立ち上がる市民と専門家の支援
5.ソーラーシステムの人見先生、汚染現場に
6.子どもに環境教育
7.立ちおくれる県の公害行政
8.現場観察で汚染土取り残し発見
9.汚染土除去の講習会に参加
10.草の根議員全国大会の開催
▲▲第6章 水源地への企業誘致計画と住民訴訟
1.土地公社理事会で誘致計画発表
2.強引な誘致計画に怒る市民
3.市民側は「地下水汚染シミュレーション」で対抗
4.チラシ合戦と「ウソ」の発表
5.訴訟の決意、誰が原告になる?
6.進出企業は公害マークだった
7.名水訴訟を闘う市民の態勢
8.判決は「公害の未然防止の願い」却下
9.日本の公害裁判は市民に立証責任
10.アメリカは、企業に立証責任
11.市民の示した名水訴訟への意思
▲▲第7章 環境保全の夜明け
1.草の根選挙で環境派市長を送りだす
2.NHK出版の「大野の豆腐はなぜうまい」
3.情報公開と環境教育
4.ホタルのために河川改修を変更した県土木部
5.市が天然ブナ林のナショナルトラストを
6.中野清水を市民が復活
7.情報公開条例の成立
▲▲第8章 地下水蘇生プロジェクトチームを結成
1.専門家の応援をえて市民による本格的調査を再開
2.「おいしい地下水」の水質
3.農薬と地下水汚染
4.O-157事件と大腸菌群問題
5.清滝川探訪
6.地下水蘇生の六つの提言
▲▲第9章 古い政治体質とコンサルタント体勢
1.古い議会体質
2.自治体の政策立案能力
3.コンサルタントと行政の癒着
4.市、過去の資料を整理し公表
5.“ハコモノ”政治を支える県民性
6.審議会は行政のかくれみの?
7.イトヨ対策に見られる水哲学欠如
▲▲第10章 合併浄化槽への取り組み
1.汚染処理行政の2人の先覚者
2.石井式合併浄化槽+木炭トレンチ併用実験
3.実験でわかった意外な発見
4.合併浄化槽実験の総括
5.地域への波及
6.実験を通し汚水処理の原点を考える
▲▲第11章 大野市の上下水道政策と地下水
1.二兎を追う「名水保全」と「上下水道」
2.農業集落排水事業
3.動きだした大野市下水道計画と地下水
4.地下水の視点が欠けた下水道政策
5.水を考える会の対策試案
6.かくされていた国の下水道計画見なおし案
7.ことを急ぐ利権集団の背景
8.工事現場の大量出水
9.下水道政策を考える
10.拒否された提言
11.下水道政策の見なおし議会で追及
▲▲終章 いのちの水よ、よみがえれ
1.地下水問題の根源
2.いのちの水を100年後の子孫に残すために
3.いのちの水をまもるための具体的提案
4.議会よ、さようなら
5.21世紀ヘの若いうねり
内容説明
水行政にかかわる住民運動のモデルケースとして、全国で注目を集める活動リポート。
目次
第1章 手おくれの地下水対策―昭和四九(一九七四)年~昭和五八(一九八三)年
第2章 議会へ出て知る地方政治の実情―昭和五八(一九八三)年~昭和六〇(一九八五)年
第3章 トヨタ財団の助成と市民の調査活動―昭和六〇(一九八五)年~昭和六三(一九八八)年
第4章 名水シンポジウム開催と国の水政策転換―昭和六〇(一九八五)年~昭和六三(一九八八)年
第5章 地下水汚染と専門家の支援―昭和六〇(一九八五)年~平成二(一九九〇)年
第6章 水源地への企業誘致計画と住民訴訟―平成三(一九九一)年~平成五(一九九三)年
第7章 環境保全の夜明け―平成六(一九九四)年~平成九(一九九七)年
第8章 地下水蘇生プロジェクトチームを結成―平成六(一九九四)年~平成一〇(一九九八)年
第9章 古い政治体質とコンサルタント体勢―平成元(一九八九)年~平成一一(一九九九)年
第10章 合併浄化槽への取り組み―平成三(一九九一)年~平成一二(二〇〇〇)年
第11章 大野市の上下水道政策と地下水―平成元(一九八九)年~平成一一(一九九九)年
終章 いのちの水よ、よみがえれ―平成一〇(一九九八)年~平成一二(二〇〇〇)年
会員の声