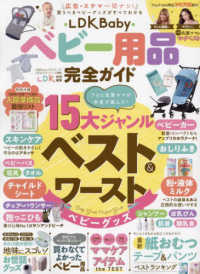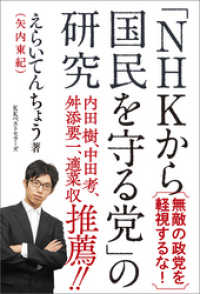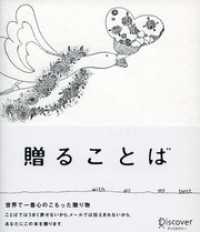出版社内容情報
防災関係者、必読の書。毎年のように発生する豪雨・台風水害は日本の宿命なのか? わが国に見られる水害の2つのタイプ、過疎地の水害と都市・都市近郊での水害について、統計資料の分析とフィールドワークによる実態調査から、いくつかの事例を取り上げ、その原因を究明し、具体的な対策を論じる。 ●●●本書「あとがき」より抜粋=第1章では、日本の水害の全体像を明らかにしようとした。まず、被害金額の移動平均からは、水害被害は減少傾向にはないことを示した。一方、死者・行方不明者数は、減少傾向にある。情報の伝達システムや避難体制の確立が進むにしたがい、一度に1000名を超える犠牲者の発生は見られなくなった。しかし、現在も100名を超える犠牲者を生む年が、しばしば見られる。第2章では、過疎地の水害を対象に、実態調査から、被害構造を明らかにした。過疎地の水害は土砂災害をともなうものが多く、犠牲者も多い。しかも被害は社会的弱者に集中して現れる。被害は単年度にとどまらず、その影響が長期に及ぶことが明らかになった……(中略)……地域の資源を用いた、内発的な経済発展がどこまでできるかと、水害の克服は、密接な関わりを持っている。第3章では、都市近郊の水害を事例にあげた。都市近郊は都市化のなかで、地価の相対的に安い水田から、スプロール的に都市的土地利用に転用されていく。もとの地目である水田は、湛水機能を有していたのだから、わずかの盛り土程度では浸水を防ぎきれない……(中略)……地域の水を管理する視点で、流域の土地利用規制が進められる必要がある。第4章は都市の水害を論じた。近年、都市の内部の中小河川が、水害原因になることが多い……(中略)……都市の内部で水害常習地が多発している。水害防御施設の建設とともに、非構造的水害対策もとられるようになった。水害対策は行政だけの仕事ではない。地域住民を主体とした「町づくり」のなかに、水害対策が組み込まれることが必要である。この視点がないと、水害克服過程でしばしば生まれる、地域活性化の芽は摘み取られてしまう。●●● 【主要目次】▲▲第1章・一級河川の水害動向からみた日本の水害=水害研究の課題/日本の水害/明治以降の水害動向/1961年以降の水害動向/原因別被害金額の推移/被害金額の変化と単位面積当たりの被害金額の変化/河川等種類別被害金額の推移/河川別にみた水害構造/日本の河川の区分/洪水比流量からみた日本の河川/河川ごとの被害金額/洪水比流量と一般資産等被害金額/氾濫危険区域の面積と人口 ▲▲第2章・過疎地の水害---福島県大沼郡金山町における水害と就業構造の変化=過疎地の水害/被害激甚地の変貌/1969年災害の概要/水害が農家に及ぼす影響/復旧工事の進展/金山町の土建業の実態/滞留する労働力/集団移転と共同農業/集団移転の概要/大岐集落の共同農業 ▲▲第3章・都市化地域における水害と住民の対応---埼玉県中川流域の水害を事例に=都市水害とは/中川流域の概要と水害史/中川流域の位置/中川流域の地形/瀬替と用水系の開発/排水河川の現状/中川流域における水害史/中川流域の都市化と水害の頻発/中川流域の人口急増/中川流域の土地利用の変化/都市近郊地域の水害特性/原因別・河川別被害金額構成からみた中川流域水害/1966年から1979年における中川流域の水害/1980年代の中川流域の水害/草加市の水害と住民の対応/草加市の水害概要/水害常習地の社会構造/水害への対応策としての盛り土/水害パーセプション/工場にみられる水害対策/地域水害対策 ▲▲第4章・都市水害=都市水害の深刻化/東京の水害/「東京の水害」の被害の特徴/目黒川の水害発生と住民の対応/水害常習河川化した目黒川/出水状況/被害状況と対応策/都市の水害対策/総合治水対策の課題/洪水防御策/流出抑制政策/氾濫原管理/耐水建築/警報システム/水害保険/水害実績図の公表と住民が水害危険区域を認識することの喚起/河川協議会
内容説明
毎年のように発生する豪雨・台風水害は日本の宿命なのか?わが国に見られる水害の二つのタイプ、過疎地の水害と都市・都市近郊での水害について、統計資料の分析とフィールドワークによる実態調査から、いくつかの事例をあげ、その原因にせまり対策を論じた、防災関係者必読の書。
目次
1 一級河川の水害動向からみた日本の水害
2 過疎地の水害―福島県大沼郡金山町における水害と就業構造の変化
3 都市化地域における水害と住民の対応―埼玉県中川流域の水害を事例に
4 都市水害