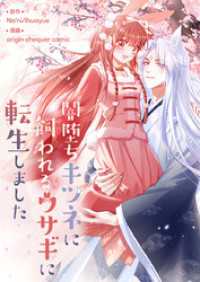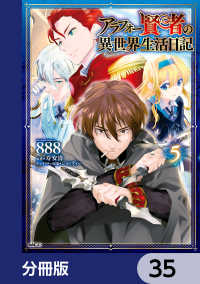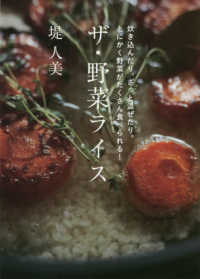内容説明
「配膳したら異物を口に入れてしまった!」「利用者の部屋にも危険がある?!」「ほかの利用者に対応している間に転倒?!」など…。事故やけがを防ぐために、介護職としてできること、すべきことを解説。
目次
1 利用者への言動や対応(拒否や抵抗があっても、時間内に入浴介助を終えるのが優先?!;利用者同士の喧嘩にはかかわらないほうがよい?! ほか)
2 介護場面(移動・移乗;食事関係 ほか)
3 薬や感染などにかかわる対応(服薬介助はセットされている薬を飲ませればよい?!;医師や家族に伝わったのは誤った情報?! ほか)
4 環境整備(センサーを設置していれば安心?!;掲示物は画びょうで留める?! ほか)
著者等紹介
神吉大輔[カンキダイスケ]
社会福祉法人奉優会「特別養護老人ホーム下馬の家」事業所責任者、兼「特別養護老人ホーム等々力の家」管理統括責任者。1981年東京都生まれ。介護福祉士・介護支援専門員。2006年に社会福祉法人奉優会に入職。介護職、生活相談員などを経て、現在は、法人内で事故予防、不適切ケアや身体拘束防止などの研修にたずさわる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
更紗蝦
24
移動とか姿勢とかの身体面での介助に関しては、介護士側の注意力と技術力でリスクを下げることは可能ですが、被介護者側のメンタルの問題、特に、「介護を受けるのは屈辱」と感じてしまっている場合の対策法は、実質、ないも同然なのでは…と思ってしまいました。「タイミングや気分を変える」「ゆとりを持って接する」「想いをくみ取る」等のアドバイスは、「介護のされ方」に不満がある場合にのみ有効なのであって、「介護されているという状況」に不満がある場合は、対処のしようがありません。介護問題で一番やっかいなのは、そこなのでは…?2022/04/15