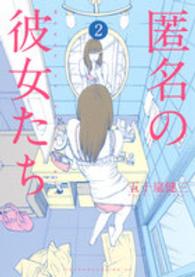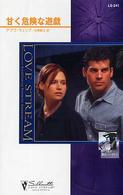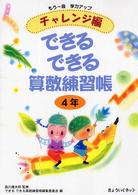目次
第1章 梵天勧請思想と神仏習合―仏教の平和思想を支えるもの
第2章 共生の試みに関する一考察―インドネシアの宗教と社会
第3章 長谷川如是閑と老子
第4章 エズラ・パウンドと能楽―その翻訳作品の意義について
第5章 「もう1つの成熟」としての老い―「老い」についての哲学的考察
第6章 インターネットの構造と、社会との共犯関係について
第7章 日本語母語話者の大学生の考える英語授業内の日本語使用について―習熟度別の比較
第8章 韓国地方都市における中心商業地形成の歴史的過程
第9章 仏教的寛容思想と日本的寛容“和(やわらぎ)”思想の意義
著者等紹介
保坂俊司[ホサカシュンジ]
中央大学政策文化総合研究所研究員・中央大学国際情報学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マウンテンゴリラ
3
私を含め、仏教に関心のある人間にとって、その歴史において、教義およびその信仰地域の変化の幅が、他宗教に比べ極端に大きいという点についての疑問はあるだろう。その理由として本書で挙げられているのが、仏教の寛容性であり、多神教的多様性であるということだろうか。そのように、寛容性、多様性といったことが、普及と衰退の諸刃の剣であるとは思いたくないが、現在のアメリカ大統領選の経緯などを見るに、寛容性、多様性が、不寛容性や悪しき一神教的固執による分断に飲み込まれようとしている現実を見れば、→(2)2020/10/20