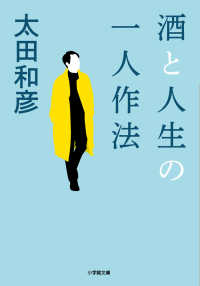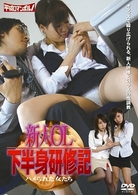出版社内容情報
■内容紹介
悔しかったら、
優勝してみろ!
そう檄を飛ばした2020年の独自大会では、
西東京と東西決戦をともに劇的なサヨナラ勝ちで完全優勝。
直後の秋季大会も制してセンバツ出場。
いま激戦区・東京で圧倒的な勝負強さを誇る、
東海大菅生の「昭和流」指導論!
著者は、以下のように述べています。
「褒めて伸ばす」が平成・令和の指導法だとすれば、私のような「褒めない」
「叱る」が主軸の指導法は「昭和スタイル」だといっていいだろう。
ただ、現代の「褒めて伸ばす」という教育は当初の理念からは離れ、「何でもかんでも褒めればいい」という安直な方向に向かっているような気がしてならない。何でもかんでも叱りつけるようなやり方はもちろんNGだが、何でもかんでも褒めるようなやり方も、選手の成長を阻害するものでしかないと私は思う。
本書では、私がなぜ今の指導法に辿り着いたのか、そして今、どのような指導をしているのかを具体的に記していきたいと思う――本文より
■目次
第1章 高校野球超激戦区、東京~甲子園出場は容易ではない~
選手との距離を縮め2015年、初の甲子園出場~恩師の姿に学ぶ~/2014年から3年連続決勝戦敗退~監督のネガティブな思いはすぐに選手に伝染する~/2017年、清宮幸太郎擁する早実に勝ち甲子園出場 ほか
第2章 恩師に恵まれた私の野球人生~原貢監督、星野仙一監督ほか歴代監督の教え~
東海大相模入学~名将・原貢監督との思い出~/「大学でも野球をやっていいぞ」~父親からの生涯唯一のやさしいひと言~/プロ入り4年目で悲願の初勝利!/高校野球の監督になろうと思ったきっかけ/星野仙一監督は何がすごいのか ほか
第3章 叱って伸ばす~なぜ今、「昭和スタイル」の指導法なのか?~
「叱って伸ばす」の真意~人は「発憤」することで成長する~/粘り強い選手を育むには?/薄っぺらい正義感は不要~選手にとっていい人になる必要はない~/夏の大会の前に練習のピークを作る~気持ちは技術を上回る~ ほか
第4章 高校野球投手論~元プロ野球投手としての視点~
気持ちの弱い投手のメンタルを強くするには?/アウトローに投げる制球力をつけるには「まず低めに集める」/シュート系のボールはピッチャーを助けてくれる/ジャイアンツドラ1・髙橋優貴の高校時代/中学生選手を見る時、どこを見ているか ほか
第5章 東海大菅生の走攻守~基本にあるのは、守り勝つ野球~
ノックではランナーも入れてより実戦的に/根拠なき盗塁は許さない/相手の隙を突く走塁~どんな時も先の塁を狙え~/ランナー三塁の極意/元シェフが作るおいしい食事で体作り/ウエイトトレーニングで強い体を作る ほか
第6章 これからの高校野球を考える~指導者はどうあるべきか~
選手の「気付く力」を育むゴミ拾い/鬼の目に涙はない
内容説明
悔しかったら、優勝してみろ!そう檄を飛ばした2020年の独自大会では、西東京と東西決戦をともに劇的なサヨナラ勝ちで完全優勝。直後の秋季大会も制してセンバツ出場。いま激戦区・東京で圧倒的な勝負強さを誇る、東海大菅生の「昭和流」指導論。
目次
第1章 高校野球超激戦区、東京―甲子園出場は容易ではない
第2章 恩師に恵まれた私の野球人生―原貢監督、星野仙一監督他、歴代監督の教え
第3章 叱って伸ばす―なぜ今、「昭和スタイル」の指導法なのか?
第4章 高校野球投手論―元プロ野球投手としての視点
第5章 東海大菅生の走攻守―基本にあるのは、守り勝つ野球
第6章 これからの高校野球を考える―指導者はどうあるべきか
著者等紹介
若林弘泰[ワカバヤシヒロヤス]
1966年4月22日生。神奈川県出身。東海大相模ではエースとして活躍。その後進んだ東海大では1年秋からベンチ入りし、2年春には最優秀投手賞を獲得。大学時代は、首都大学リーグで通算30試合に登板して14勝4敗、防御率1.78の成績を残した。社会人野球の日立製作所では、3年目にはエースとして、都市対抗でチームをベスト8に導く。1991年のドラフトで、中日ドラゴンズから4位で指名されて入団。6年間のプロ生活は1勝1敗という結果にとどまった。引退後は運送会社の勤務などを経て、2007年に東海大菅生の教員として赴任し、2009年から同校監督に就任した。2015年に指揮官となって初のセンバツ出場。夏の甲子園初となる2017年は、チームをベスト4に導いた。2020年夏には東京独自の西東京大会と、帝京との東西決戦も制した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
tetsubun1000mg
水落健二
SAHARA
-
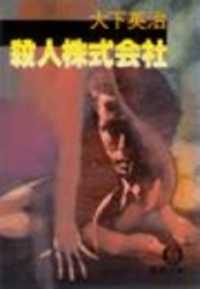
- 電子書籍
- 殺人株式会社(電子復刻版) 徳間文庫
-

- 和書
- 談志絶倒昭和落語家伝