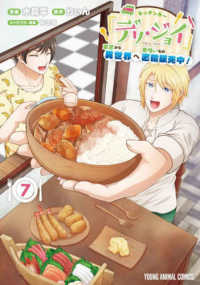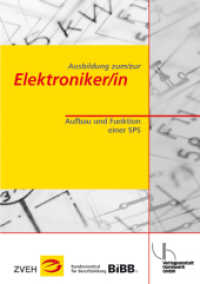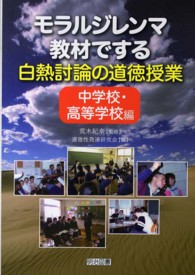内容説明
『本朝鍛冶考』に書かれていること。わが国では千年もの間、多くの刀鍛冶がより良い刀を作ろうと切磋琢磨してきた。刀剣づくりは全国各地で行われ、日本の大きな産業の一つであった。刀剣のもつ神秘性や、重器や家宝としての位置づけを伝えている。同時に、刀剣に対する審美眼を育てるための書でもあった。江戸中期刀剣書のベストセラー、初の現代語訳で甦る!「古刀」「新刀」の概念を確立した刀剣研究の第一人者・鎌田魚妙によって解き明かされた一千以上の茎の写し。
目次
巻之10 刀剣各部名称解説―機内五箇国 中心(茎)図説
巻之11 東海道十五箇国 同
巻之12 東山道八箇国 同
巻之13 北陸道七箇国 同
巻之14上 山陽道三箇国 同
巻之14下 山陽道五箇国 同
巻之15 山陰道八箇国 同
巻之16 南海道六箇国 同
巻之17 西海道九箇国 同
巻之18 諸国鍛冶 同
著者等紹介
鎌田魚妙[カマタナタエ]
1727‐1797年。江戸時代中期~後期の武士、刀剣研究家。享保12年生まれ、伊予(愛媛県)出身。西洞院時名につかえ、のち武蔵川越藩(埼玉県)藩主松平家の家臣となる。安永6年(1777)新刀研究の基礎文献となる『新刀辨疑』を、寛政8年古刀に関する本著『本朝鍛冶考』をあらわした。寛政8年12月12日死去、70歳。本著が遺作となる
内藤久男[ナイトウヒサオ]
1951年東京都生まれ。1975年日本大学大学院卒業。(一財)社会通信教育協会生涯学習2級インストラクター(古文書)。(公財)日本美術刀剣保存協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。