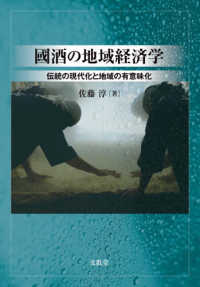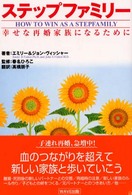内容説明
近代とは“散文の時代”。グーテンベルクの印刷革命による“文字/活字の文化”の覇権は、言葉から“声”を奪い、それを“目”の言語へと変容させた。私たちは“声”なき“散文の時代”を生きて久しい。視覚化された言語が産み落とした“散文”とは何かを問い直し、記憶による思考から成る“声の文化”の行方を英米文学・日本古典文学・文化人類学・環境文学など多岐にわたる視座から探る試み。
目次
第1部 テクストの“声”を聴く(視点なき思想―反散文論のほうへ;声の残響―ハーマン・メルヴィル『白鯨』の口誦性;小説、舞台、教室―声が織りなす『フランケンシュタイン』 ほか)
第2部 聴覚空間の文化(説話の第三極論―声と文字の往還;文章の“型”の獲得―学校教育における美辞麗句集;声と音のペダゴジー―音響共同体としての大学 ほか)
第3部 “声”から“声”へ(語りかける文学の予祝―島尾ミホと石牟礼道子を中心に;野生の中へ―石牟礼道子の口承的な文学世界を翻訳するということ;石牟礼道子の「声音」の思想 ほか)
著者等紹介
野田研一[ノダケンイチ]
1950年生まれ。立教大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
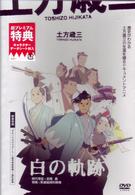
- DVD
- 土方歳三 白の軌跡