内容説明
「人類学の存在論的転回」を主導する著者の初期の代表作。16世紀、ブラジル沿岸部に住んでいたインディオ・トゥピナンバは、当時のイエズス会宣教師たちには御しがたく、耐えがたい民であった。彼らが見せる「気まぐれさ」ゆえに…。宣教師たちによって残されたテクストを丹念に読みながら、彼らとはまったく異なる方法で、インディオ・トゥピナンバの社会哲学や“存在論”を鋭く読み解く。
目次
一六世紀ブラジルにおける不信仰の問題(宗教体系としての文化;地獄と栄光について;楽園にある区分;信仰の困難について)
トゥピナンバはいかにして戦争に負けた/戦争を失ったか(時間を語る;古い法;記憶の汁;強情な食人者たち;気まぐれさをたたえて)
著者等紹介
カストロ,エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ[カストロ,エドゥアルドヴィヴェイロスデ] [Castro,Eduardo Viveiros de]
1951年、ブラジル・リオデジャネイロに生まれる。リオデジャネイロ連邦大学ブラジル国立博物館教授。文化人類学者、民族誌学者。アマゾン地域の先住民研究を専門とする
近藤宏[コンドウヒロシ]
1982年、静岡県に生まれる。立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了。博士(学術)。現在、国立民族学博物館外来研究員、立命館大学非常勤講師。専攻、文化人類学・南米低地民族誌
里見龍樹[サトミリュウジュ]
1980年、東京都に生まれる。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。現在、日本学術振興会特別研究員。専攻、文化人類学・メラネシア民族誌(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三柴ゆよし
roughfractus02
袖崎いたる
s_i
V
-

- 電子書籍
- 再実装Flutter - UIフレーム…
-
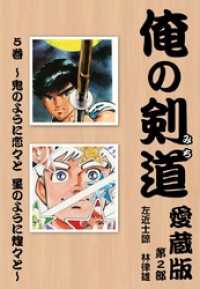
- 電子書籍
- 俺の剣道 愛蔵版 第五巻 ~鬼のように…







