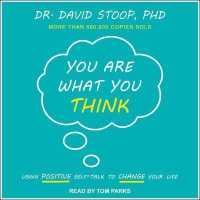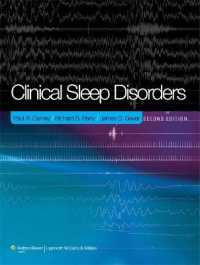内容説明
「報徳秘稿」として、明治に至るまで門弟の座右に秘められていた草稿。全471章から成る幻の名語録を復刻。二宮尊徳が遺した語録の精髄。
目次
巻1(世界と文化の開びゃく;天祖のあしあと ほか)
巻2(忠孝を知慧とする;高い山から谷底見れば ほか)
巻3(人心危く道心微かなり;誠なれば明らかなり ほか)
巻4(大久保彦左衛門の深慮;大久保忠隣への親書 ほか)
巻5(武王の討伐を批判する;聖人の道と子どもの遊び ほか)
著者等紹介
斎藤高行[サイトウタカユキ]
1819‐1894。文政2年生まれ。江戸後期‐明治時代の農政家。陸奥中村藩(福島県)藩士。二宮尊徳の高弟。嘉永4年から叔父富田高慶をたすけ、中村藩領で報徳仕法を指導した。維新後、興復社、相馬報徳社を設立。明治27年没。通称は粂之助
佐々井典比古[ササイノリヒコ]
1917‐2009。大正6年佐々井信太郎の長男として小田原に生まれる。昭和16年東京帝国大学法学部卒業。17年内務省採用、間もなく応召。神奈川県研修室長、人事課長、労働部長、総務部長、副知事、神奈川県内広域水道企業団企業長を歴任。58年より報徳博物館長・一円融合会、財団法人報徳福運社・財団法人大倉精神文化研究所各理事長を歴任。平成21年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
n-shun1
0
ところどころ二宮翁夜話と重なる。同じエピソード。弟子がそれぞれに書いているし,同時期に一緒に聞いたのかもしれないし,尊徳が繰り返し話していたのかもしれない。積小為大,譲道,分度,一円融合,悟道と人道の違い,禍福や男女,親子,君臣,この世は対となるもので作られている=故に中こそ至高,種草花実はいずれも同じもの,等のお話。尊徳は酒を飲まないというのが発見だった。父親は酒が好きで,小さい頃の父親のために酒を買ってくるエピソードもあるが,酒にも徳はあるが,それを上回る悪徳になりがちとのこと。法が廃れると。反省。2024/06/26