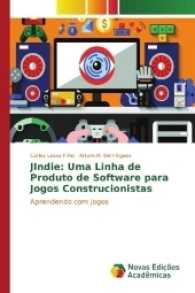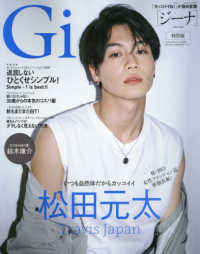内容説明
あの江戸幕末の時代に1発の銃弾も撃たず、1滴の血も流さず、600以上の村を甦らせた人がいた。面白くて一気に読める、七代目子孫が語った知られざる二宮金次郎一代記。
目次
第1章 多くの人に愛され、育てられた金次郎
第2章 すべてはまず「知る」ことからはじまる
第3章 金次郎がぶつかった人間関係という壁
第4章 すべてのものにはプロセス=徳がある
第5章 報徳とはtake and give
第6章 「報徳」こそ目の前の現実を豊かにするための秘訣
第7章 どんなときも一歩踏み出すことを忘れなかった金次郎
著者等紹介
中桐万里子[ナカギリマリコ]
昭和49年東京都生まれ。神奈川県で育つ。二宮金次郎(尊徳)の7代目子孫。慶應義塾大学環境情報学部卒業。その後、京都大学大学院教育学研究科に進学し、臨床教育学を学ぶ。平成17年同大学院にて教育学の博士号を取得し、課程修了。19年より「親子をつなぐ学びのスペース『リレイト』」を主宰。国際二宮尊徳思想学会常務理事、聖和大学専任講師を経て関西学院大学講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
5 よういち
59
【TP1401】二宮金次郎の7代目子孫の著者が金次郎の生き方を教えてくれる◆薪を背負って本を読んでいる像の二宮金次郎については、実はそれ以上のことは知らなかった。勉強熱心な人くらい...しかし、そこには色んな誤解があった。いやあ、なんかドタマを殴られた感じ...◆二宮金次郎の像は勉強の大切さを教えるものではなく、一歩を踏み出した足が大切。どんな時も行動することを教えているのだという。/金次郎の発想の原点は目の前の事実を受け止めて、解決すること。/困ったときほど、相手を知ることに努める。それが解決のヒント2018/08/07
Gotoran
26
7代目子孫の著者が、農民でありながら農村再建の指導者となり六百以上の村を復興させ江戸末期に活躍した二宮金次郎の生き方・考え方を紹介。昭和の小学校にあった「薪を背負って本を読む」金次郎像。その姿が教えるのは勉強の大切さではなく一歩踏み出した足。すなわち、どんな時も行動することを忘れてはいけないと。全ては知ることから。報徳とはtake and give。独学での神道、仏教、儒教等と農業実践で至った在り方金次郎(尊徳)の報徳思想(至誠、勤労、分度、推譲)。まさに豊かに生きるための智恵。気付き・学びに溢れていた。2014/02/02
Tomoko 英会話講師&翻訳者
8
二宮金次郎の7代目子孫が書かれた本。たきぎを背負って本を読む人というくらいの認識しかなかったけど、農村でいろんな改革をやった行動派だったとは。知識だけを入れるのではなく、実践すること。行き詰ったら現場に行って現実をよく見ること。2016/09/20
kasugaitaro2011
5
最も大切なのは、一歩を踏み出している足。「実践することを何よりも大切にしなさい」。■半円の見:一方からだけの見方。「主役は誰か」一円で見た一人ひとりが主体性を発揮し、力を尽くせるシステムが必要。■うつ心:「加害者は誰か」■水車と川:川が無ければ水車は廻らない。同時に水車が川を活かしている。■困ったときほど、相手を知る。相手に飛び込むことが大切。2014/03/04
Thugio Nakadachi
1
give and take ではなく、take and give。私達は、先祖や、自然、周りの方達のお陰で、今がある。ありがたいな~、幸せだな~だからその徳に応えよう。ありがとう探しの達人になることが、自分の心の田を豊かにする秘訣ですね。おすそ分けは、喜んで頂けると本当に嬉しいですね2013/11/27
-

- 電子書籍
- 未来人カオス - 2巻