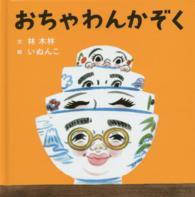内容説明
ミャンマーという国名よりビルマと言った方が日本人には分かりやすいかもしれないこの国で、民族・宗教・政治が複雑に絡み、錯綜する社会の狭間で命をつなぐ人びとの生業に分け入り、行脚をかさねた東南アジア紀行文学の決定版。
目次
1 ミャンマーの国家・民族・宗教(宗教統計というものの危うさ;メーサームレップへの旅―民族への接触 ほか)
2 ミャンマー現代文学に寄せて(ミャンマーという国の「アジア的」概念;『漁師』 ほか)
3 ミャンマーの鉄道昨今(二〇一一年七月一一日(月)―ヤンゴン循環鉄道
二〇一一年八月一三日(土)、一七日(水)~一八日(木)―ピー(PYAY) ほか)
4 ヤンゴン五景(アウンサン将軍邸のプルメリア;露天屋台食堂 ほか)
著者等紹介
熊澤文夫[クマザワフミオ]
1941年名古屋市生まれ。横浜市立大学でフランス文学を、京都大学で昆虫生態学を学ぶ。永く生態学方法論の研究を続け、従来の「生態学とは生物の生活を研究する学問」という定義を、独自に「生態学とは関係の学としての生物学」とより包括的な、新しい定義付けを試みる。1987年よりタイを中心にインドシナ半島を行脚し、居住して、特に異文化の意義について考え続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。