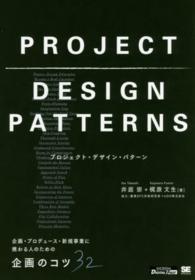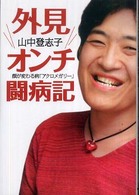出版社内容情報
本書では、葬儀やお墓に関する「謎」を選んで項目をたて、その起源、変遷、意味などを解説することで、 まず日本の葬送の「しきたり」や死生観の変遷をたどる。さらには、現代の葬式事情(直葬、自然葬など)にも触れながら、多死社会に向かうなか、今後どう変わるのか、あるいはどうあるべきなのかにも触れつつ 、日本人の死生観の原風景を探る。
内容説明
葬式は誰のためにするのか、なぜ墓をつくるのか―日本人の死生観、葬儀形態が変化するなかで、「いま」あらためて、葬送に関わる「しきたり」、日本人の「死生観」を、歴史からひもとく。
目次
1章 人間は死んだらどこへ行くのか?―仏教・儒教の死生観と日本古来の霊魂観
2章 なぜ火葬が「普通」になったのか?―土葬と火葬の受容史
3章 亡くなった人はいつ「死者」になるのか?―天皇家に残った葬法「殯」とは?
4章 葬式のメインは、告別式ではなく、葬列だった?―古代~現代の葬送の変遷
5章 なぜ戒名をつけ、位牌をつくるのか?―「葬式仏教」の本来の意味とは?
6章 なぜ葬式に香典を持って行くのか?―葬式にかかわる「お金」の問題
7章 通夜、葬儀、告別式はどこがどう違うのか?―宗教・宗派で異なる葬式スタイル
8章 なぜ四十九日に納骨するのか?―日本の葬式に残る喪と忌みの習俗
9章 お墓参りはいつから行われるようになったのか?―墓地に映し出される日本人の先祖観
10章 なぜお盆に先祖供養が行われるのか?―仏教と民俗信仰の融合
著者等紹介
新谷尚紀[シンタニタカノリ]
1948年広島県生まれ。現在、國學院大学文学部および大学院教授。国立歴史民俗博物館名誉教授・総合研究大学院大学名誉教授。社会学博士(慶應義塾大学)。早稲田大学第一文学部史学科卒業。同大学院文学研究科史学専攻博士後期課程単位取得
古川順弘[フルカワノブヒロ]
1970年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。宗教・歴史分野をメインとする編集者・ライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
木ハムしっぽ
とんぼ
海戸 波斗
-
![眠れないのは月のせい[comic tint] 分冊版(11)](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2159571.jpg)
- 電子書籍
- 眠れないのは月のせい[comic ti…
-

- 電子書籍
- 週刊文春臨時増刊 マイナンバーが誰にで…