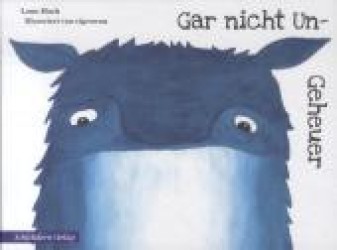出版社内容情報
知識が日本酒を旨くする!飲む前に知っておきたい、味わうための日本酒学。
内容説明
知るほど旨くなる!新しい日本酒の世界。かつての「おじさんの酒」というイメージは一新され、若手蔵、若手杜氏たちの挑戦により、再び脚光を浴びている日本酒。「おいしくなった!」と言われる日本酒だが、今までと何が違うのか。銘柄を選ぶ際の手助けとなる、名称やラベルの読み解き方、流行の味わい、これまでの歴史まで、よりおいしく飲むための知識を凝縮!
目次
第1章 飲み手のための日本酒の新常識(日本酒の定義;日本酒が悪酔いするは迷信! ほか)
第2章 造りで味わう(日本酒造りの流れ;日本酒の味はどこで決まるか ほか)
第3章 歴史と味わう(日本酒のもとになった酒は僧侶が造っていた;江戸の酒は今の日本酒と変わらない ほか)
第4章 地元の酒を知る(全国日本酒巡り;日本酒ラベル図鑑 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
izw
14
日本酒を味わいが、原料である米、水の違い、造り方の違いで、どのようにバリエーションが増えるかが、簡明にわかり易く解説されている。これまで、何度も日本酒造りの過程を読んできたが、すぐに忘れてしまい、混乱してしまっているが、この本の解説は、非常にわかり易く、ポイントが異なる観点から何度も記載されているので、良く分かる。酒を呑むとき、手元に置いておきたい一冊である。2017/02/23
めぐねい
6
あー、どおりで読みやすいと思ったら2年前に読んでいたのか。二回目だから読みやすいってわけではなく、文章量やトピック、ページ構成など、バランスが良かったんだろうな。2年か、、、この本を読んでから試験も受けてないし、一ノ蔵の無鑑査も飲んでいない。2年も経ったのに成長していない私。あ、飲む日本酒の量は増えてたし(それは違う意味での成長というのではないか?)銘柄には詳しくなった。分類で味を決めつけることが増えてしまったので、初心にかえって、純粋に日本酒を楽しもうとは考えている。ただ、いまだに泥酔しちゃうのはなぁ。2023/05/28
nemuro
6
日本酒好きですので、この種の本をなんとなく購入することも多いのですが、読了本は、おそらく初めて。たまたま読み始めのあたりで、「日本酒は冬から春にかけて造られ、9月くらいまでの間、蔵の中で貯蔵されます。秋の訪れとともに出荷する日本酒を『ひやおろし』とか『秋あがり』と呼びます」なんてところを読んでいて、行きつけの居酒屋で「豊盃 あきあがり」が「期間限定ですよ」って出されたので、そのウンチクを語ったところ、大将から「その本、読み終わったら貸して!」と言われたせいでもありますけれど。2016/09/24
めぐねい
4
日本酒についての本はたくさん読みましたが、これは文庫版サイズなので手に取りやすく、中を見ると文字多いなという印象を受ける割に読みやすいです。読み始めるとあっという間です。しかも知識も吸収しやすく、再読したいなと感じました。うんちくが嫌味でないのですねぇ。スーパーでよく見かける一ノ蔵の無監査のを飲んでみたくなりました。とりあえず買っておきます。酒米がもっと作られるようになって、日本酒造りに携わる人も増えて、結果として日本酒を飲む人が増えて欲しいのですが、入手困難なお酒がこれ以上増えるのも困ります(^^; 2021/10/03
ココアにんにく
3
初心者でもわかりやすいように丁寧に書かれていた。普通のお米と酒造好適米の違い。普通に炊いたらどんな味?なんで蒸すの?疑問だった事も書かれていた。酒米も減反対象だったなんて!。親がよく飲んでいた「剣菱」のすごさ。三増酒時代にも信念。どぶろくとにごり酒の違いも分かった。本書は灘のとある郷の図書館で見つけました。p143宮水のキャプション(神戸市→西宮市)です。もっと歴史の古い伊丹よりなぜ灘のお酒が江戸で飲まれたのか。海の近さだった!2018/03/01
-

- 電子書籍
- THE QUEEN~稀代の霊后~【タテ…
-
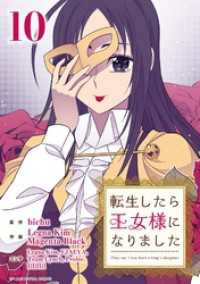
- 電子書籍
- 転生したら王女様になりました(10) …