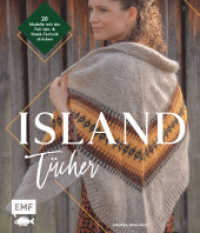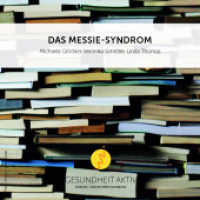内容説明
私達の先祖は、どんな武器で戦い、何が原因で死傷したのか?20数年の歳月と2000件の事例をベースに、戦闘員の死傷原因・手柄・使用武器の実相を探る、日本軍事史研究の壮大な試み!
目次
第1部 戦場での死傷原因と手柄(なぜ合戦の実態に興味を持ったのか?;戦闘の実態は何からわかるのか?;「戦闘報告書」から得られた死傷例;手柄の実態と死傷例)
第2部 死傷例から見た合戦の現場(中世合戦のイメージ;軍忠状と軍記物のギャップ―南北朝期の合戦;「刀鎗併用時代」の虚実―戦国前期の合戦;鉄砲が主武器となった時代―戦国後期の合戦)
第3部 「手柄」はいかに評価されたか(「戦闘報告書」で主張された功名;褒めらる功名、褒めにくい功名)
最後に確認しておきたいポイント(軍隊の組み立てと戦いの主体;「白兵主義」は古来からの伝統?;集団化はいつからか)
著者等紹介
鈴木眞哉[スズキマサヤ]
1936年横浜市生まれ。中央大学法学部卒業。旧防衛庁、神奈川県庁等に勤務。歴史研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
9
戦闘といえば白刃チャンバラ。現代のテレビシーンに欠かせない戦国時代の白兵戦闘の誤解は何故生じたか、偃武以降も伝統観念として残ったこの由来に挑む。著者は歴史文書を丹念に漁り、鎌倉末から江戸初期までの戦闘における死傷者の原因解明を試みる。結局どの時代でも、戦場で刀傷報告は少なく、圧倒的な多数は、中世においては矢傷と槍傷、石と礫、戦国以降はこれに鉄砲傷が加わる。猪武者が一番槍を求めて突進しても、直ちに弓矢や鉄砲で殺されてしまうのが実態だった。信長が鉄砲によって戦闘に革命を起こしたという神話についても述べられる。2024/08/28
gauche
4
「感状」や「注文(要求されて提出した戦闘報告書)」から南北朝から戦国の合戦の様相を分析し、刀剣は戦闘の主体ではなかったということをあらためて裏付けている。弓矢や石つぶてが主体となると、合戦のイメージが描きづらいなあ。へぇと思ったのは暗殺したりだまし討ちにしたり、あるいは秣の刈り取りに出た人たちを無事に撤収させたりした人にも感状が出されていたということ。2017/01/05
m_syo
1
軍忠状や戦闘報告書類から、中世のリアルな戦場の様子を描き出した本。著者の熱い思いが伝わってきて、楽しく読めた。2015/07/29
史
0
遠戦という現実と、白兵戦という浪漫。2018/10/26
-

- 和書
- にっぽん心中考 文春文庫