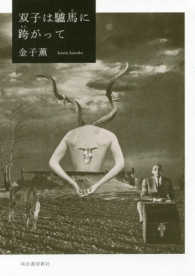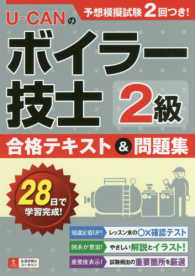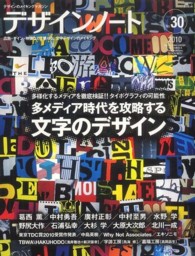内容説明
「お客様はこのサービスをご利用できません」―マニュアルどおり丁寧に伝えたのに、なぜかお客さんは「君、失敬だな!!」と怒っている。このように日本語の使い方ひとつで“炎上”事件に発展することもあります。あなたの言葉がよく誤解されるのは、あなたの使う日本語が間違っているからかも。その「間違い」に気づいていないのが「勘違い」。勘違いの日本語を使っていると、あなたの真意が伝わりません。上から目線な「感心しました」、生意気に聞こえる「お休みをしてもいいですか?」など、勘違いしがちな日本語を、『明鏡国語辞典』(大修館書店)でおなじみの北原保雄先生がきっちり解説します。
目次
第1章 伝わらないのは敬語の使い方を勘違いしているから
第2章 勘違いの言い方では敬意は伝わらない
第3章 使い方を勘違いした敬語
第4章 “ぼかし”表現では伝わらない
第5章 勘違い日本語はバカだと思われる
第6章 伝わる日本語を身につけるために
著者等紹介
北原保雄[キタハラヤスオ]
1936年、新潟県生まれ。国語学者・日本語学者、文学博士。筑波大学名誉教授・元学長。現在、新潟産業大学学長。多くの国語・古語辞典の編纂に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
25
言葉というものは変化するものだ。辞書に載っているから正しいとか、載っていないから間違いだと判断するのではなく、本来の意味や使い方に照らして、どの程度適正であるかを自分で考えることが必要だ。言葉は変わるものなので、それは仕方がない。しかし、重要なのは、言葉は伝承し、受け継がれながら徐々に、かつ部分的に変わって行くものであり、それが望ましい。 子供が大人と言葉を交わす機会の減っている環境下、やはり、本を読み、辞書を引く習慣が重要だと指摘する。変化するものだが徐々に変わるもの。それが言語としては、相応しそうだ。2019/08/07
myc0
15
30回目となるビブリオバトル発表本であり、12回目のチャンプ本。著者は、明鏡国語辞典を作った日本語学者•北原保雄。彼の本は、高校時代に「問題な日本語」を読んで以来。「飛ぶ鳥跡を濁さず」など元の慣用句を知っている人なら明らかに間違いに気づく慣用句や敬語の誤用表現を、どうして間違えて使われるようになってしまったか、その背景と文章の構造を丁寧に解説する。この本のすばらしい所は、言葉の変化や誤用を指摘し、それを責めていると言うわけでは無いところ。言葉は時代によって変化していくものだと言うことを踏まえ、2015/06/20
モモのすけ
11
「敬語は、誰に敬意を表すのか、高める対象を見極めること。相手を遠ざける効果もある。大切なのは聞き手に対する思いやりである」と。敬語は難しい。ちゃんと使っているつもりだったがまだまだであった。2013/04/30
Yoshinori Osaka
10
「新年、明けましておめでとうございます。」も誤りだったとは(>_<)2015/07/30
愛奈 穂佳(あいだ ほのか)
5
【ココロの琴線に触れたコトバ】伝わるということだけでいえば、敬語を使わないことが一番通じやすいのです。二重敬語も敬語連続も日本語のしくみとしては間違っているわけではありません。しかし銀メッキの上に金メッキをするように、敬語の使い過ぎは問題だということです。2014/11/22