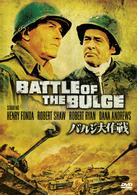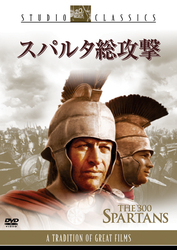内容説明
和の技術のひとつ「弁当」をテーマに、日本の文化に親しみながら、楽しく知識を深められる本です。おもな弁当の種類を知り、さらに日本の各地域の特色ある弁当を見て、日本の弁当の豊かさを学びます。昔から受けつがれてきた弁当づくりのスゴ技を、老舗弁当店や駅弁店を通して知り、さらに家庭の弁当づくりを助ける便利なグッズを見ていきます。江戸時代に使われてきた手のこんだ弁当箱と、今の機能性にすぐれた弁当箱やエコを意識した弁当箱を紹介します。外国でつくられる弁当にはどんなものがあるのか見てみましょう。国際Bentoコンテストの作品も紹介します。子どもが献立づくりから買い物、調理、かたづけまですべて自分でおこなう「弁当の日」について、どんな様子か見てみましょう。「もっと弁当を知ろう」では、おもに日本で発展した弁当の歴史や進化や、弁当にかかわる仕事につく方法など、さらに深く弁当を学んでいきます。
目次
弁当の世界へようこそ
弁当の技を見てみよう
昔と今の弁当箱いろいろ
世界の弁当を見てみよう
「弁当の日」を楽しもう!
もっと弁当を知ろう