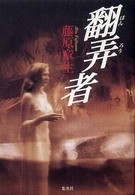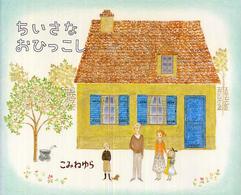内容説明
現在、理科の学習内容と時数が増えたことで、授業をこなすことに注力してしまい、「何のために」、「何を」子どもに獲得させるのかという本質的な議論が希薄になっている傾向があるようです。理科は、本来、子どもが自然の事物や現象とかかわることによって、人間性を豊かにしていくことが目的でした。本書は、この本来の目的を実現するために、どのような指導をすればよいかを明らかにしています。教育基本法、学校教育法などの読み解き、自然科学と理科の違い、内容区分の考え方などといった、理科教育の成り立ちや仕組みの理解から始め、その上で、問題解決の授業、総合的な学習、言語活動ではどのように指導し、評価すればよいかについてまとめています。
目次
第1章 現在の日本の教育はどのような方向を目指しているのか
第2章 自然科学と理科は何が違うか
第3章 なぜ、理科の学習内容が領域別になっているのか
第4章 理科における問題解決の授業をどうつくるのか
第5章 学力をどのように評価するか
第6章 理科授業と言語
第7章 理科授業と算数
第8章 理科と総合的な学習の時間
著者等紹介
角屋重樹[カドヤシゲキ]
昭和24年三重県生まれ。広島大学大学院教育学研究科教科教育学(理科教育)専攻博士課程単位取得退学。博士(教育学)。広島大学教育学部助手、宮崎大学教育学部助教授、文部省初等中等教育局教科調査官、広島大学教育学部教授、広島大学大学院教育学研究科教授、国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部部長を経て、日本体育大学児童スポーツ教育学部教授、広島大学名誉教授、国立教育政策研究所名誉所員、日本教科教育学会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。