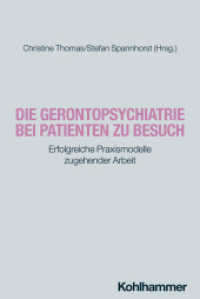内容説明
社会や家族のあり方が変わればお墓のあり方も変わる。核家族化、都市化、出生率の低下や未婚率の上昇、高齢化等により、日本では現在、さまざまなお墓の問題が起こっている。一人っ子の長男・長女が「実家のお墓をどうするか」という問題、独身で家族がいない高齢者が自分のお墓をどうするかという問題、転勤が多い人がお墓をどこに作るかという問題、離婚した親の墓をどうするかという問題等々…。本書は家族とお墓の変遷を振り返り、お墓をめぐる意識の調査・分析を通して、家族をどう弔うか、ひいては家族とどう向き合うか考えるヒントを提供するものだ。
目次
第1章 日本の家族はこんなに変わってきた(江戸時代以前、「家族」という意識は薄かった;江戸時代に生まれた、現在につながる家族の形 ほか)
第2章 家族が変わればお墓も変わる(外国のお墓はどうなっているのか;日本のお墓も時代によってずいぶん違う ほか)
第3章 「お墓、どうしますか?」アンケートとインタビューで意識調査(アンケート調査(量的調査)に見る意識
インタビュー(質的調査)に見る意識)
最終章 家族もお墓もいろいろあっていい(父の死によって生じた家族の変化;お墓は誰のためのものか? ほか)
著者等紹介
米澤結[ヨネザワユウ]
マスコミ勤務後、結婚を機に退職。その後、墓と家族について研究するため大学院に入り、修士課程を修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たなかはん
3
先日家内の実家の墓を墓仕舞いしたり、自分の実家の墓の先行きを考えはじめたり、墓についてはいろいろ考えることが多くなってきて、世間の方々は墓の問題とどのように向き合っているのか興味があって手に取った。 日本の墓をとりまく文化的な変遷と、いろいろな人への聞き取り調査の結果が書かれている。墓については色んな考え方や立場の人がいるなと思ったが共感も抱いた。 『小谷(2011)』のような記載があちこちに出てきて、何かなと思ったら引用した文献の著者とその刊行年度だということが巻末を見てわかったが読んでいて邪魔に思う。2018/07/18
myary
0
外国では火葬が始まると、さっさと帰ることも。遺体に対する執着が、アジアとヨーロッパでは違うようだ。宗教の違い、先祖信仰など、様々に要因はあるが、今まで当たり前に身の回りに起きていたことは、世界という視点からみると、決して当たり前ではないことだったのだなと分かった。
-

- 和書
- ちょっと怠けるヒント