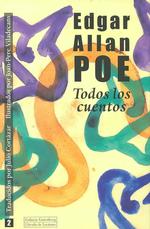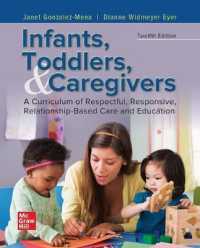内容説明
60年ぶりの改革が始まる!政治と結びついた既得権益「悪玉論」はいま、本当か?6次産業化した農業が、日本の明日を変える!
目次
第1章 JA改革で何が変わるのか―捻じ曲げられたJA改革(改革の3つの柱;JAをめぐる背景の変遷 ほか)
第2章 JAとは何か―知られざるJAの実態(JAとは何か?;JAの歴史 ほか)
第3章 JAの功罪―刷り込まれている日本農業の常識、非常識(JA悪玉論の本質;農政の代理人としてのJA ほか)
第4章 日本の農業に未来はあるか(日本の農業のあるべき姿;食料自給率は指標にならない ほか)
第5章 農業の将来に向けてJAができること(JAは生まれ変われるか;もうかるJAをつくる ほか)
著者等紹介
杉浦宣彦[スギウラノブヒコ]
中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授。中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了博士(法学)。香港上海銀行、金融庁金融研究研修センター研究員、JPモルガン証券シニアリーガルアドバイザーを経て、現職。金融庁特別研究員、日本資金決済業協会特別理事、JAグループ自主改革有識者会議座長。金融法やIT法が専門分野だが、現在、福島などで、農業の6次産業化を進めるために金融機関や現地中小企業、さらにはJAとの連携等の可能性について調査、企業に対しての助言等も行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
60
筆者は、JAグループの自主改革に関する有識者会議の座長を務めた直後にこの本を執筆した様である、末尾にやるせない思いを本にした、と記されている。そう、恐ろしく長大重厚なJA=農協という組織に踏み込めていないな、というのが読書中からの所感である。但し、そうした面は否めないものの、僕の場合は外郭的に自身の仕事上の知識として得たい面あり、それらは断片的に学べ、言葉を得られたのである。2020/05/24
Daisuke Oyamada
26
2015年刊行なので少し古めの印象は隠せませんが、私は「JA=悪の組織」という、そんなイメージを受ける本を何冊か読んでいたせいか、少しJAを見直させてくれる内容でありました。 政治と結びついた既得権益「悪玉論」は本当なのか。6次産業化した農業が、日本の明日を変えるという。 農村票を武器に、戦後最大の圧力団体といわれてきた農協の改革。なぜ、この時期で、何が問題なのか。 日本の農業・・・ https://190dai.com/2024/06/14/jaが変われば日本の農業は強くなる-杉浦宣彦/2024/06/15
としP
13
米の減反は今はほとんど廃止されているようだが、その理由が、農業就業者の減少による需給ギャップ縮小だったとは・・・。/農家を法人化するという考え方には否定的なようだ。その理由は以下が重くのしかかるからだ。①税負担の増加②事務処理の増大③社会保険の加入により経費の負担④労務管理の必要性⑤農業の世界に会社法的な企業統治の考え方がどこまでマッチするかは難しい。/JAが農家をリードして、安定的に農業に従事できる環境を作り、儲かるようにしなくてはならない。農業の6次産業化を推進すべし。2019/12/05
dowalf
11
2015年、2月のJA改革により、これからJAはどうなっていくべきかを述べた一冊。何となく日本の農業にとって悪者のようなイメージがあったJAですが、この本の筆者はJAの持つ可能性に焦点を当てています。JAが日本の農業のあるべき姿を正しく見据え、戦後獲得してきた流通網や人材等を活かせば、日本の農業が成長産業となるために必要な、6次産業化や農地改革の担い手になる事ができるのでは、という視点で書かれています。TPP交渉が大筋合意し、農業が変化すべき今、国内でやるべき事が少し見えてくる気がしました。2015/11/18
スダタロー
5
今春の農協改革を踏まえて、今後の国内農業のあり方を農協を通して見た本書。日本の農業が農協なくして語れない以上、現状そして将来を見据えて農協自体の付加価値を向上させることはなくてはならないと言えます。一度衰退した産業を復活させることはなかなか困難なことですが、農協も主要アクターの一つとして課題解決に取り組んでいってほしいです。2015/10/03