内容説明
よい文章を正確に書き写す。それは、学問するための基礎体力を養う。読み書き教育は“からだ”を育てることなしにはあり得ない。その意味で、体育なのである。学生は他人の文章をその通りに書き写し、一点一画、一字一字を意識する。学生に書き換える自由はない。この不自由が学生に語の異同を意識させる。学生は語の選択について闘い始める。文章の書き手との論争をするに到る。“からだ”に読み書きさせる実験授業報告。
目次
序論 なぜ視写を課したのか
第1章 読み書き教育は体育である
第2章 “筆触”とマス目
第3章 写し間違いは思考を刺激する
第4章 「私ならこう書く」―学生の主張
第5章 異同の意識
第6章 “からだ”の鍛え方―早稲田大学「学術的文章の作成」授業と比較する
補遺 「『書く』っていいなあ」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
良さん
1
視写でこれほどの書く〈からだ〉が作られるとは驚きだ。また書くことと読むことがつながるということも、追試してぜひ実感してみたい。 【心に残った言葉】「抵抗感」=〈筆触〉が強いと、「文章を確かめながら書くことにつなが」る。…触覚は、書く意識だけではなく、読む意識も変える。(51頁)2012/02/10
MIRACLE
0
大学一年生向けの必修科目「日本語表現」での授業実践を中心に、視写による教育とその効果について述べた本。視写とは他人の文章を一字一句、正確に書き写すことだ。指導の対象となった学生のほとんどは読み書きの経験が絶対的に不足していて、表記、語法の規準が身についていない。そのため、文章を書けない。作文を指導する以前に、作文を書くことができないのだ。そこで、筆者は宿題として「私の履歴書 石坂公成」全三十回分を継続的に、原稿用紙に視写させ、それをもとに指導を行った。本書は視写の劇的な学習効果を伝えていて、参考になった。2025/05/18
-

- 電子書籍
- 爛漫ドレスコードレス(37) カルコミ
-
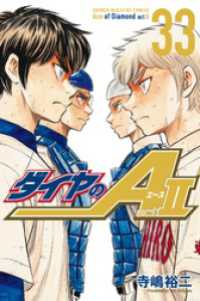
- 電子書籍
- ダイヤのA act2(33)
-

- 電子書籍
- Fishing Cafe VOL.73…
-

- 電子書籍
- 恐竜キングダム(2) 海中探検は危険だ…
-
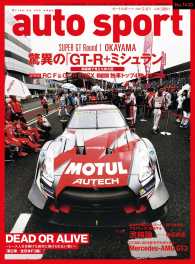
- 電子書籍
- AUTOSPORT No.1430 A…




