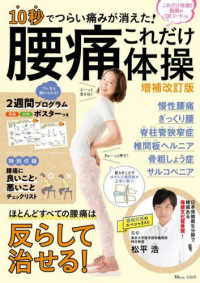- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
出版社内容情報
バルト三国の一つ、ラトヴィアにある図書館が本書の主人公である。この国で図書館は「光の島」、「光の点」などと呼ばれてきた。ラトヴィア人にとって、光は「知識、文化、自己成長」を意味しており、図書館を想起させる言葉となっている。人口が200万人に満たないこの国にある公共図書館数を人口当たりで換算してみると、日本の15倍以上となる。驚異的なこの数字は、「公共図書館大国」と言われるスカンジナビア諸国をも圧倒している。なぜ、こんなにもたくさんの公共図書館が小さい国の隅々にまであるのだろうか。
ラトヴィアが旧ソ連から独立したのは1991年。それから30年余り、占領期に弱体化させられた自国語と失われた文化遺産を取り戻すために、図書館界は館種を超えて連帯し、図書館の再構築にひたむきに邁進してきた。その象徴とも言える存在が、2014年に完成した「新国立図書館」、通称「光の城」である。
開館に先立ち、同年1月18日に最初の資料の運び入れがはじまった。その日はマイナス15度という極寒。そんな日に、約15,000人もの市民が旧館から新館まで手渡しで資料を移動させたのだ。列の長さは約2キロに及んだという。そう、世界中の関係者が新国立図書館を知ることになった、「光の道:本の愛好者の鎖」である。
本書は、ラトヴィアの図書館の歩んできた道のりとじっくり向き合い、小さな国の図書館のパワーを解明するためのものである。ラトヴィアの図書館は、読書をこよなく愛する人びとによって支えられている。本を循環させる社会装置の一つとして図書館は、そうした人びとの読書欲を満たすために、あらゆる手段で読書へのニーズに応えようとしてきた。熱心な読者と図書館の相互対話的な営みが、少数話者言語であるラトヴィア語の記録とラトヴィア文化の記憶を継承する回路の中軸となっている。学ぶべきことが満載のラトヴィアの図書館、ページを繰りながら旅をしていただきたい。
内容説明
バルト三国の一つ、ラトヴィアにある図書館が本書の主人公。この国において図書館は「光の島」、「光の点」などと呼ばれてきた。この国の人びとにとって図書館は「言語文化を守る砦」であり、社会を照らす「光」であるからだ。それを証明したのが、15,000人もの市民が旧国立図書館から新館に手渡しで本を運んだシーンである。日本では考えられないような光景の秘密を探るために、筆者はラトヴィアに飛んだ。そして目にしたのが作家、出版社、公共図書館の連携によって繰り広げられている「読書空間」だった。
目次
第1章 図書をめぐるストーリー―言語・出版・図書館
第2章 ラトヴィアの公共図書館―二度の占領を乗り越える
第3章 ラトヴィア公共図書館のサービス
第4章 光の城・ラトヴィア新国立図書館
第5章 光の島・リーガ中央図書館
第6章 ラトヴィアと日本の図書館について語り合う
著者等紹介
吉田右子[ヨシダユウコ]
筑波大学図書館情報メディア系教授。博士(教育学)。専門は公共図書館論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobuko Hashimoto
練りようかん
お抹茶
ふじひよ。
かふん
-
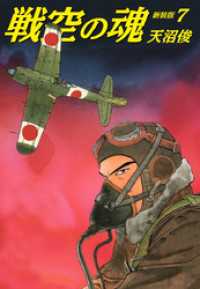
- 電子書籍
- 戦空の魂 新装版 7
-

- 和書
- 管理主義教育 新日本新書