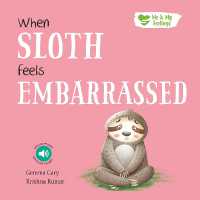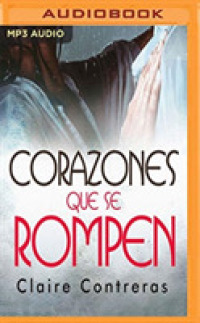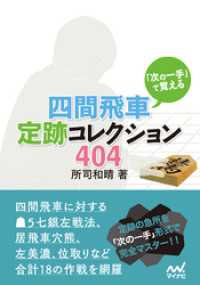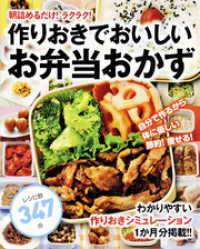出版社内容情報
トラクターと戦車、化学肥料と火薬、農薬と毒ガス。農業を変えた発明は、戦争のあり方をも変えた。増大する人口を支えるシステムの闇に光を当て、飽食と飢餓の狭間で、危機に瀕した食の本質を考える。
内容説明
農作業を効率的にしたい。その思いが二十世紀の農業技術を飛躍的に発展させ、同時に、その技術が戦争のあり方をも変えた。トラクターは戦車に、化学肥料は火薬になった。逆に毒ガスは平和利用の名のもと、農薬に転用される。本来人間の食を豊かにするはずのテクノロジーの発展が、現実には人々の争いを加速させ、飽食と飢餓が共存する世界をつくった。この不条理な状況を変えるために、わたしたちにできることを考える。
目次
第1講 農業の技術から見た二十世紀
第2講 暴力の技術から見た二十世紀
第3講 飢餓から二十世紀の政治を問う
第4講 食の終焉
第5講 食と農業の再定義に向けて
第6講 講義のまとめと展望
著者等紹介
藤原辰史[フジハラタツシ]
京都大学人文科学研究所准教授。1976年、北海道生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中途退学。京都大学人文科学研究所助手、東京大学大学院農学生命科学研究科講師を経て現職。専門は農業技術史、食の思想史、環境史、ドイツ現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1959のコールマン
69
☆5。名著。ただし「戦争と農業」では内容を誤解する人が多数いると思う。「食べるという人間の原初的かつ基礎的行為を根本的に考えること」がこの本の中心テーマだからだ。内容は広範囲かつ濃い。前半は農業と戦争と飢餓。それぞれの関係性を詳細に記述。後半は「食べること」を中心に論を進める。そして結論は、単純な「答え」を出さないで、「答え」を導き出すための方法論を提示。これはこれで正解だろう。様々な要素が複雑に絡み合っている現代社会では、「はい、これをすればエコです」といった単純な「答え」はかえって有害だから。↓2021/03/14
アナクマ
40
好評「トラクターの世界史」よりも作者の考えが包括的に理解できるかなと先に読了。競争という仕組みが肥大化した結果失われた公平性を、食と農業の再定義を足がかりにして変えていけないかと模索している、という立ち位置。人口増加を支えた四大農業技術が戦争をも支えた構図、食糧の分配と争いの歴史を描き出します。◉(作者も構想しているとおり)現場での実践と研究とを往復して、口当たりが良いだけではない骨太で剛健な哲学を構築して欲しいと期待を込めて思いました。支持したい、柔らかな主張の本。2017/12/18
skunk_c
36
『トラクターの世界史』の著者が「大学付き食堂」と名付けた市民講座での6つの講話を書籍化したもの。本書のタイトルは最初の2講で、3講以降はそこから広く企業活動、食、教育などに広がっていく。『トラクターの世界史』がなぜ面白いのかが分かった。この著者は確かな人間観、自然観を持っているのだ。人間を多くの生物が存在する中の「細いチューブ」と捉え、自然との共生を着実に目指すような社会哲学が通底しており、社会を巨大企業の利益収集装置から人間主体のゆっくりとした時間が流れる社会に変えようという壮大なヴィジョンがあるのだ。2017/11/15
おかむら
35
「トラクターの世界史」に比べると、言葉は悪いが女子ども向けっつーか、優しい口調でかなり読みやすい。中高生むけ。こういう歴史の切り取り方で授業を受けてたらもっと世界史に興味出てたと思う。ナチスドイツの飢餓作戦とか全然知らなかったなー。ただこの本後半は食育とかエコロジーとかの話になっちゃってその手の本はたくさんあるから、もっと歴史視点で語って欲しかった感。2018/01/11
さきん
32
窒素の工業による生産は大量の肥料を得た分、大量の弾薬を作ることも意味していた。また、トラクターは農作業を楽にした面が大きいが、小さい農業を破壊し、戦争では戦車に発展した。戦争で使われた毒ガスは農薬になった。後半は、日本で食、農の営みをどう取り戻していくかについて。読みやすい。2018/01/04