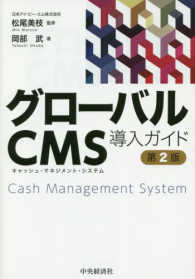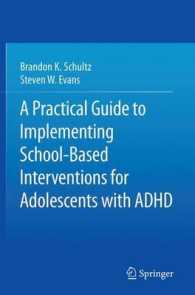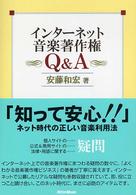内容説明
地球の軌道上には、世界各国から打ち上げられた人工衛星が周回し、私たちの生活に必要なデータや、宇宙の謎の解明に務めています。本書は、いまや人類の未来に欠かせない存在となったこれら人工衛星について、歴史から各機種の役割、ミッション状況などを解説したものです。
目次
第1部 人工衛星はこんなにおもしろい!(1機の人工衛星には無数のストーリーがある;人工衛星に携わる無名の技術者がつむぎだすストーリー;人工衛星はどこにいる?;衛星の姿勢を保つ仕組み ほか)
第2部 宇宙と地球を見つめる・護る人工衛星100(人工衛星の歴史と未来黎明期の人工衛星たち;もっとも身近な天体「月」を目指せ;とどまることなく新しい技術に挑戦する衛星たち;志半ばで散った衛星たち ほか)
著者等紹介
中西貴之[ナカニシタカユキ]
1965年、山口県生まれ。ポッドキャスト科学番組「ヴォイニッチの科学書」において、最新の人工衛星の技術や観測成果を紹介する「シリーズ今週の人工衛星」を制作中。日本科学技術ジャーナリスト会議会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
植田 和昭
10
美しい人工衛星を扱った本。天空に展開されたアンテナは、幻想的ですらある。日本の人工衛星おおすみも出てくる。無誘導ロケットで人工衛星を軌道投入したところがすごい。今やれと言われても無理だろう。ここで確認したいのは、最初の人工衛星を打ち上げたのは旧ソ連だということだ。アメリカは敗れた。これは歴史的事実である。以来アメリカではスプートニクショックにより科学教育が見直されて理科の学習には、実験助手やアシスタントがついて3人で教えるが、日本はどうだろう。他の教科よりむしろ軽視されているような気がする。科学立国?無理2025/04/06
たー
10
一口に人工衛星といってもいろんな目的や種類があるんですね~2012/06/26
ちくわん
7
ハッブル宇宙望遠鏡の影響で読む。しかし、天文マニアでもメカマニアでもない小生にはいささか退屈。衛星には、観測(地上、宇宙)、探査(月、惑星、太陽など)、放送・通信・GPS、新技術の実験など様々。米露欧日が多いが、ここもやがて中か?2019/04/06
karasu
3
重力の制限を受けないから、いろいろな形があって面白い。2011/06/15
た〜
2
テクノロジーの追っかけの楽しさを改めて実感させてくれる。さすがサイエンスコミュニケーターを務めている著者だけのことはある