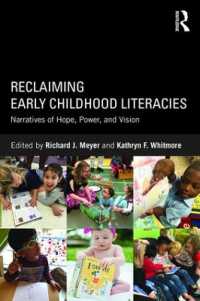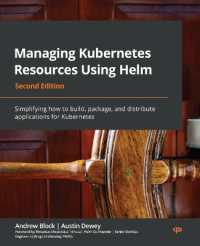出版社内容情報
法曹関係者、必読の書!
日本初となる、官民協働で運営する「PFI刑務所」を
実現させた著者が語る“日本の刑務所の未来像”!
民間のノウハウを取り入れた官民協働の刑務所として知られている「PFI刑務所」。現在、全国に四つの社会復帰促進センター(PFI刑務所の呼称)があります。このPFI刑務所を一から築き上げた現役の法務省大臣官房審議官である著者が「日本の刑務所の未来像」をはじめて語ったのが本書です。PFI刑務所とは何なのか、公権力が行使される刑務所をなぜ官民協働にしようと考えたのか、どのようなメリットはあるのか、地域住民の受け入れ態勢はどうだったかなどの疑問にすべて答えています。本書は、自身の経験から法務省が考える刑務所のあり方までを誰にでもわかりやすく説いた、まさに「日本の刑務所入門書」といえます。
見城美枝子氏(ジャーナリスト・青森大学教授)からの推薦コメント――西田博審議官は信念の人です。今までにない民営刑務所構想に法務省はどう動いたのか……。本書は、PFI刑務所が開所するまでの経緯と、著者の人徳と情熱を記録した「西田ファイル」の“読む”ドキュメンタリーです。
西田博(にしだ ひろし)
1954年生まれ。高知県出身。
法務省大臣官房審議官(矯正局担当)。
1977年中央大学法学部を卒業後、法務省に入省。以降、盛岡少年刑務所長、法務省矯正局総務課国際企画官、広島矯正管区第二部長、法務省矯正局参事官、法務省大臣官房参事官(矯正担当)、法務省矯正局総務課長などを歴任。2011年4月より現職に就任。
内容説明
今までにない民営刑務所構想に法務省はどう動いたのか…。PFI刑務所が開所するまでの経緯と、著者の人徳と情熱を記録した「西田ファイル」の“読む”ドキュメンタリー。日本初となる、官民協働で運営する「PFI刑務所」を実現させた著者が、これからの“刑務所”の在り方を問う。
目次
第1章 地域共生型刑務所誕生
第2章 官民協働による地域共生型刑務所
第3章 日本の刑務所の実情と官民協働の模索
第4章 再犯率ゼロを目指す社会復帰促進センター
第5章 日本のコミュニティ・プリズンとして
著者等紹介
西田博[ニシダヒロシ]
1954年生まれ。高知県出身。法務省大臣官房審議官(矯正局担当)。1977年中央大学法学部を卒業後、法務省に入省。以降、盛岡少年刑務所長、法務省矯正局総務課国際企画官、広島矯正管区第二部長、法務省矯正局参事官、法務省大臣官房参事官(矯正担当)、法務省矯正局総務課長などを歴任。2011年4月より現職に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヤギ郎
takizawa
saku_taka
vonnel_g
ちか