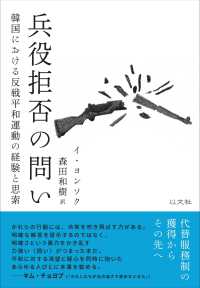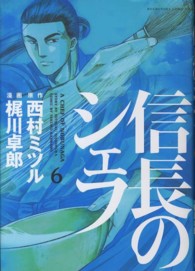内容説明
この国では「戦争ができる国づくり」への動きが強まっている。しかし、いくら法律を整備しても戦争はできない。それをになう国民の「心」が求められている。教育基本法改正、道徳副教材『心のノート』の全小中学生への配布、有事法制など、平和憲法離れが加速する時代の根底にあるものを思想的に分析し、どのように生きるかを問う注目の書。「国民精神」はいかにして創出されてきたか。戦死者が英雄視され、さらなる戦死者を生みだしていく回路を断ち切るには―。「心」と「国」と「戦争」をめぐる現代の危機を、戦前からの大きな流れの中に見すえた「いま、生成する」哲学がここにある。
目次
第1講 道徳副教材『心のノート』の思想(日常化する道徳教育;四段階で心を形成 ほか)
第2講 愛国心と選別―教育基本法「改正」が狙うもの(子供の心が因われる;憲法改正への一里塚 ほか)
第3講 「有事法制」はこの国をどう変えるのか(「軍事優先社会」がやってくる;新たな「非国民」の析出 ほか)
第4講 「靖国」―戦死者追悼の過去と未来(なぜ首相の靖国参拝が問題になるのか;神道は宗教でなくて道徳? ほか)
著者等紹介
高橋哲哉[タカハシテツヤ]
1956年、福島県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻、哲学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
寛生
25
【図書館本】「命の大切さ/重み」を考える人たちや哲学・政治学を研究者にとってこれは必読書。著者が、デリダの息子/弟子らしく「この時代」について「心」と「戦争」の2語をあげて2002年文部科学省から小中学生に配布された「心のノート」を主に「脱構築」していく。哲学者とは、そして知識人とはこういうものなんだと、高橋先生の鋭い批判・指摘、議論の展開に息を呑む。議論の展開はデリダのそれを思い出させるが、彼の怯まない知識人としての態度はデリダを超えて行く。我々は、彼の警告をよくよく聞きとどめておくべきだろう。2013/11/29
katoyann
15
教育基本法「改正」と有事法制の成立が取り沙汰されていた2002年に朝日カルチャーセンターで開かれた講演をまとめたもの。教育基本法改正の特徴は国家主義と競争主義にあった。つまり単純素朴な復古主義だけではなく、グローバル化の大競争時代の国家戦略として、国家の人材として役立つエリートを育てる一方で、残りの大半を「国策」に協力する忠良な愛国者に育てることが目的だと言う。 例えば、オリンピック開催に併せて都合の良いように緊急事態宣言を濫発する国家の無策を批判できなくする。今の民主主義の破壊に繋がっている話だ。2021/07/09
frosty
6
図書館で、目的も何もなくふらついていたら目についた本。借りてみた。内容はずっしりと重くて、読み進めるのが時々辛くなるほど。でも、知っておかなきゃいけないことだから、知っておかなきゃいけないと思うから、どうにか読了。十年くらい前に出版された本で、情報もそれなりに古い。だから、今はこの陰謀?がどこまで進んだんだろう?戦争を体験したことも、身近に体験したことがある人が近くにいることもない私は、今の社会でどれほど甘えた考え方を持っていたのだろう、って。もし本当にこのまま日本が軍事国家になったらってって怖くなった。2015/01/30