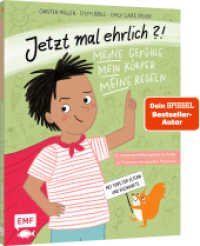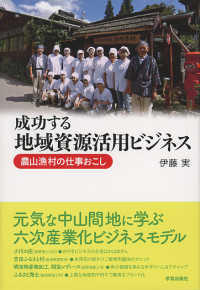- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
内容説明
美しい書物はどのようにしてつくられてきたか。中世イギリスの辺境の島で修道僧たちによってつくられた福音書。グーテンベルクやカクストンら初期印刷術者によってつくられた書物。そして、ウィリアム・モリスの理想の書物―。書物の美しさの精髄を豊富な図版を駆使して解き明かす。本を愛してきた人間の情熱とその運命を人間味あふれる数々のエピソードをまじえて物語る、たのしい書物の文明史。
目次
第1章 中世の彩飾写本
第2章 初期印刷術
第3章 彩色図版のあるイギリスの書物―1790‐1837
第4章 プライヴェート・プレスの時代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
jamko
9
翻訳物の専門書だし難しいかな…まあチラ読みでも…と読み始めたら読みやすいわ面白いわで1日で読み終えてしまった。著者は中世の写本と印刷の発明以降をきっちり分断する。写本文化を終わらせたのは印刷の発明だが、印刷の発明は人類を進化させた。写本は美術品でありメディアにはなり得なかったという視点は、そのままウィリアム・モリスの晩年の矛盾も突く。書物への静かなパッション溢れる文章も大変好み。2018/10/14
のんき
2
良くも悪くも<ロンドンで稀覯書専門書店の店主をしていた人が書いた本>でした。いい仕事してますねぇの世界。こちらの知識の圧倒的な少なさが申し訳なくなりつつも、好きなもの美しいものについて語る楽しさ嬉しさは伝わってきました。 ただ、そういう内容なのに、この本自体はあまり美しい出来上がりになっていないところが悲しいかも…。2009/05/20
あずきずき
1
ウィリアム・モリス展を観てから、図書館で見つけた本書。序盤は飾り文字(ケルズの書)の説明もあり、楽しく読めた。中盤辺りは 全く知らない人物ばかりで 勉強不足で楽しめず。終盤でモリスやコブデン・サンダスンの作品を楽しめる。2017/03/06
ヤクーツクのハチコ
1
装飾本というと、中世修道院の話が中心だけど、これは希少本古本屋店主作だけあって、マーケットに流通した印刷本に主眼がおかれてて、今まで気にも止めてない視点だったから新鮮だった。時々顔を見せるヨーロッパキリスト教的優越心が鬱陶しかったけれど、それはそれで、伝統ある古書店の店主の性質も垣間見れるということか。装飾本の写真が多いところはヨロシイ2012/10/07
-
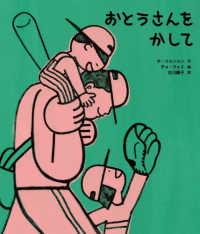
- 和書
- おとうさんをかして
-

- DVD
- 2018サガン鳥栖 イヤーDVD