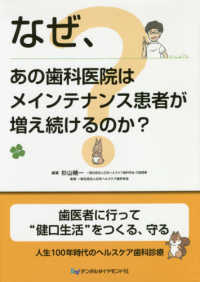内容説明
京都、中西印刷。活版印刷では日本有数の技術をもつことで知られる老舗が、コンピュータによる電子組版を導入することになった。難問山積のなか、活版時代の名人芸に負けない品質の組版・印刷のノウハウをあみだしてゆくまでの書き下ろしノンフィクション。
目次
鉛活字が消えた日
1 印刷屋の息子
2 活字が輝いていた時代
3 名人芸の限界
4 ついにコンピュータが登場
5 悪戦苦闘
6 漢字という魔物
7 パソコン通信が生みだすもの
8 職人さんたちの活躍
9 さらば、活版
10 伝統はうけつがれたか
11 印刷の未来へ
付録 JIS78とJIS83
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
59
著者は京都で古くから続く印刷屋の二代目だ。その印刷屋が1986年から活版印刷から電算写植に移行する。その移行にまつわる記録。活版印刷は印刷の原点だ。文撰、鋳造、植字と各作業は分業であり職人の仕事だ。今でこそ誰もがPCで簡単に印刷できる時代しかしほんの20数年前はまだ活版印刷も普通にあった。昔の書籍に使われている活版印刷の活字は好きだ。味がある。残してほしいと思う。また本文に出てくるPC8801やMS-DOS、ハードディスクが40MB・・・・懐かしくもあり技術の早すぎる進歩を感じた。2016/09/01
阿部義彦
22
古書市にて入手。94年刊、晶文社。これは大興奮のドキュメントでした。京都の中西印刷という日本有数の活版印刷の技術を持つことで知られる老舗が、コンピーューターを導入して電子組版を導入する事になった経緯を、同社の専務取締役の著者が綴ったものです。父である社長は活版印刷には誇りを持って、自社では今は使われない古い字体の活字を日本一抱えて、仏教書や経典などの専門書には他の追随を許さないと胸を張るが、息子はパソコンにのめり込んでゲームをプログラムする迄になるが、家業を継ぐ事に。92年6月には活版を廃止する事に。2024/10/30
Kazuo Ebihara
3
創業明治4年の京都にある中西印刷。新旧漢字を含む10万種の活字を持ち、学術印刷や公文書印刷などの活版印刷を得意としていた。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットが混じった日本語の文章をバランスよく組版にするには名人芸の技術が必要だった。1985年に入社した6代目が電子組版の導入を発意。当時はコンピュータへの指示はコマンド入力、フロッピーのメーカー間の互換性の無さ、JIS漢字コードの頻繁な変更など。数々の難問を解決し、1992年には活版印刷を完全に止め、電子組版切り替えに成功するまでのノンフィクション。2023/01/15
Isuke
3
活版印刷の老舗、京都の中西印刷。活版から電子組版への移行の記録。刊行から15年経った今、DTPの現場は活版の存在さえ、歴史へと葬られてきている。未来をつくる現場でこそ、活版現場の知識と経験を知っておく必要があると感じた。2009/08/25
どすきん
2
舞台となった時代、大漢和辞典の仕事もするし電算もこなす会社に居た。業界から離れて久しいが、大漢和辞典の5万字がすべて電子化されたとも聞く。一方で活版ワークショップに参加して、名刺作りを体験し、「まるで魔法を見ているようだ」と楽しんでいたりする。この本自体は電子組版で作られている筈。活版から電子組版への移行は瞬く間に進んだが、紙の本が消える日はしばらくは来ないかな。2016/10/16
-
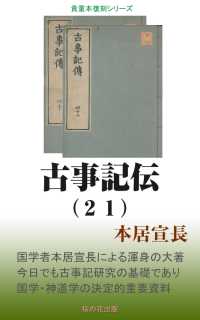
- 電子書籍
- 古事記伝(21)