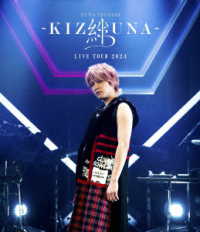内容説明
平城遷都1300年記念。初めて明らかにされた世界最古の木造建築の秘密。法隆寺の解体修理にあたった棟梁と、建築史家と、建築科の出であるイラストレーターの三人が協力、法隆寺がどのようにして建てられたかという難しい問題を解き明かした。
著者等紹介
西岡常一[ニシオカツネカズ]
1908年奈良県に生まれる。1995年没。西岡家は、鎌倉時代にはじまる法隆寺四大工の一人、多聞棟梁家につながる宮大工の家柄。明治のはじめ祖父常吉氏の代に法隆寺大工棟梁を預かる。常一氏は幼少より祖父常吉氏から宮大工の伝統技術を教え込まれ、1934年に法隆寺棟梁となる。20年間にわたった法隆寺昭和大修理で、古代の工人の技量の深さ、工法の巧みさに驚嘆したという。法隆寺金堂、法隆寺三重塔、薬師寺金堂、薬師寺西塔などの復興の棟梁として手腕をふるった
宮上茂隆[ミヤカミシゲタカ]
1940年東京に生まれる。1998年没。東京大学工学部建築学科卒業。論文「薬師寺伽藍之研究」で工学博士号を取得。1980年、竹林舎建築研究所を開設。日本建築の歴史研究と復元設計に専念した。歴史研究では古代寺院建築、中世住宅建築、近世城郭建築、数寄屋と茶室など幅広く、建築設計では国泰寺三重塔(富山県)掛川城天守(静岡県)大洲城天守(愛媛県)などがある
穂積和夫[ホズミカズオ]
1930年東京に生まれる。東北大学工学部建築学科卒業。長沢節氏に師事して絵を学ぶ。松田平田設計事務所をへてイラストレーターに。アイビーファッションのイラストなど、おもにファッションや自動車などの分野で活躍してきたが、現在では日本の歴史的な建造物や街並み、歴史風俗などを描くことに意欲的に取り組んでいる。昭和女子大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gtn
Shoji
koji
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
エリナ松岡